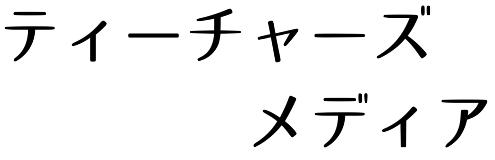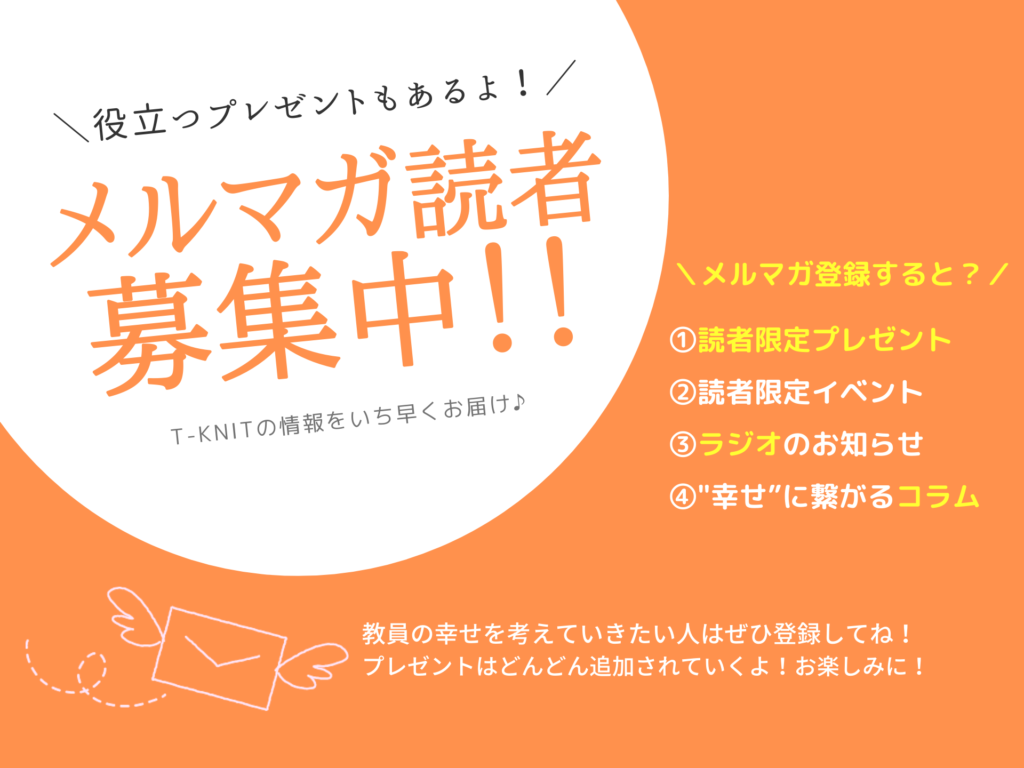- 学校運営協議会と学校評議員って何が違うの?
- 役割や、権限はどう違うの?
- 学校運営協議会ができたら学校評議員ってどうするべき?
コミュニティ・スクールを実際にやり始めようと調べてみると、なんだか似た名前がたくさん出てきますよね。その中でも似ているのが学校運営協議会と学校評議員です。
「コミュニティ・スクールの学校運営協議会と学校評議員って全く同じものじゃないの?」
「学校運営協議会に属している人のことを学校評議員って言うんですよね?」
という声が上がったりします。

名前が似てて、どうしても間違えちゃいますが、似て非なるものです!僕も間違えてた時があります(笑)
今回はその学校運営協議会と、学校評議員の違いについて説明します。しっかり覚えておきましょう!
学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)とは
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは、ものすごく簡単に言うと学校運営に対して意見を述べることができる、地域の中でも教育に対して知識や経験を持つ人たちによる『機関』です。
学校運営協議会は教育委員会や、校長に対して「これは良い」「これはやめましょう」「どうしてこの方針になったのですか?」と直接言える権利を持っていて、地域の中では学校に対してものすごく権力を持った重要な機関になります。
ちなみに学校運営協議会の設置=コミュニティ・スクールの始まりです。
学校運営協議会が学校に設置されると、地域とともにある学校作りを推進でき、学校・家庭・地域の連携等がより加速するのです。
学校運営協議会と学校評議員の違い
学校運営協議会と学校評議員は別物で、学校運営評議員という役職はありません!ものすごく間違えやすいので注意しましょう。
また学校運営協議会は学校評議会と間違えて言っている方もいるので、余計ややこしい!こちらも注意しましょう。
| 正しい名称 | 間違った名称 |
|---|---|
| 学校運営協議会 | 学校運営評議会 |
| 学校運営協議会委員 | 学校運営評議員 |
| 学校運営協議会 | 学校評議会 |
| 学校評議員 | 学校協議員 |

めちゃくちゃややこしい…!僕も任命された当初は意味が分かってませんでしたw
違いを表にするとこんな感じです。
| 項目 | 学校運営協議会 | 学校評議員 |
|---|---|---|
| 導入時期 | 2004年(平成16年)9月 | 2000年(平成12年)4月 |
| 目的 | 地域と学校が共に学校運営について考え、協同的な教育を創る | より良い学校、開かれた学校作りにする |
| 人物像 | 地域の教育有識者による合議制の機関 | 地域内外の教育有識者個人 |
| 誰がやるか | 保護者、学校に対しての協力的な地域住民、教育委員会が必要と認める者(オブザーバーとして地域外の人物を入れるのもOK) | 校長が必要と求める人物 (基本的に地域外の人物でもOK) |
| 役割 | ・校長が作成する学校運営の基本的な方針について承認と要望 ・当該学校の職員の採用その他の人事について意見 ※拘束力がある | 校長の求めに応じ、個人として意見を述べる ※拘束力はない |
| 責任 | 学校運営協議会にも一定の責任がある | 評議員に責任はない |
| 権限 | 強い | 弱い |
| 任命・設置 | 学校運営協議会の設置者(ほとんどは教育委員会)が任命 | 校長が推薦し、学校の設置者が委嘱 |

ちなみに僕は地域外の人ですが、教育委員会が必要と認める者で学校運営協議会に参加し、地域学校協働活動推進員にもなっています。かなり特殊な立場です。
大きな違いは役割と権限
学校運営協議会は学校評議員と違い、単に意見を言うだけではダメで、学校運営に参画し、校長が作成した学校方針を承認したり、意見を述べて、共に学校を作っていくという役割を担っています。
権限も学校評議員に比べて強いので、校長や、教育委員会に対して拘束力があり、意見されたことに関して「いや、それは…」みたいな学校は言い逃れが簡単にできません。
ただし、それは学校運営協議会にも一定の責任があり、共に学校を創っていくという意識を持っていないといけないのです。

単に意見だけ述べて「あとは頑張って」みたいな感じにはできません。意見を実現できるように学校運営協議会が一丸となって取り組む必要があります。だから、単なるクレーマーでは入れない機関です。
学校運営協議会ができたら学校評議員はどうするべき?
これはその地域の教育に対する考え方によって大きく変わるところだと思いますが、2つのパターンがあると思います。
- 学校評議員を学校運営協議会委員に選出し、学校評議員制度を廃止する
- 学校評議員制度は残し、1〜2人に数を絞って校長の相談役(コンサルタント)とする
学校評議員制度を廃止する
文部科学省が推奨している方法はこちらです。
<学校評議員制度に関する検討>
(資料2)今後の学校運営協議会制度等の在り方に関する方向性 – 文部科学省
- 地域の声を学校運営に反映する仕組みとして国公私立学校にまたがる重要な制度であり、現在の定着の状況等を勘案しても、制度そのものを廃止することは困難である。一方で、多くの学校で制度が形骸化しているとの指摘もあり、国は、国公私立の置かれた状況等を勘案しつつ、制度の機能化・活性化を促進する。
・公立学校については、とりわけ、小中学校を中心に、コミュニティ・スクールへの移行を積極的に促し、学校運営協議会の設置に伴い、学校評議員は廃止する。すぐに学校運営協議会に移行できない学校においては、学校評議員の合議体を形成し、学校運営全般への参画を促すことで、コミュニティ・スクールへの段階的発展を目指す。
・国立学校については、ほぼ全ての学校に学校評議員が置かれている状況であり、学校運営全般への参画を積極的に促す。
・私立学校については、学校評議員の設置状況が約3割と十分でない状況であり、学校評議員制度の意義等について改めて周知を図る。- 学校評議員からコミュニティ・スクールへの移行を促すに当たっては、学校・家庭・地域の三者の組織的・継続的な連携・協働体制が確立される、共通したビジョンをもった三者協働の取組が展開されるなど、移行による魅力・メリットを示すとともに、以下をはじめとした促進策を講じる。
・学校評議員からコミュニティ・スクールに発展する取組に対する財政的支援
・コミュニティ・スクール設置の手引きの改訂(学校評議員からコミュニティ・スクールに移行するための具体的な手順の提示等)
段階的にステップアップして、学校運営協議会を作り、学校評議員は廃止します。なぜなら、内容と人選が被ってくるからです。
不必要であると思うなら思い切って廃止に踏み切るのは良い手だと思いますし、基本的にはこちらの方向で良いかなと思います。
ただし、学校評議員を学校運営協議会委員にステップアップする場合、意見はするものの行動をしない委員になってしまう可能性が非常に高くなります。そういう可能性があると思って対策を考えておくと良いでしょう。
学校評議員をコンサルタントとして考える
これは僕個人的な考えですが、学校運営協議会ができても学校評議員を廃止せず、数を絞ってコンサルタントとして残すのはアリかと思います。
学校運営協議会ができても、話し合いの場はあくまでも『みんなで』です。そうすると校長個人の本音の意見や、考え方を出しづらいことがあります。
学校運営は基本的に学校長が行なうので、リーダーとしての苦しみを吐き出す場や、校長個人として尊重される場の形成は重要かと思っています。
本来、コンサルタントは高額ですが、それを1〜2人であるならばつけられるかもしれません。(あくまで学校予算として…ですが)
一つの案として参考にしてください。
学校運営協議会は組織、学校評議員は個人と覚えよう
では、簡単にまとめます。
この辺りを頭に入れておきましょう。
他にもコミュニティ・スクールの初歩的な内容への記事もあります。ぜひご覧ください。
その他、コミュニティ・スクールに関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。