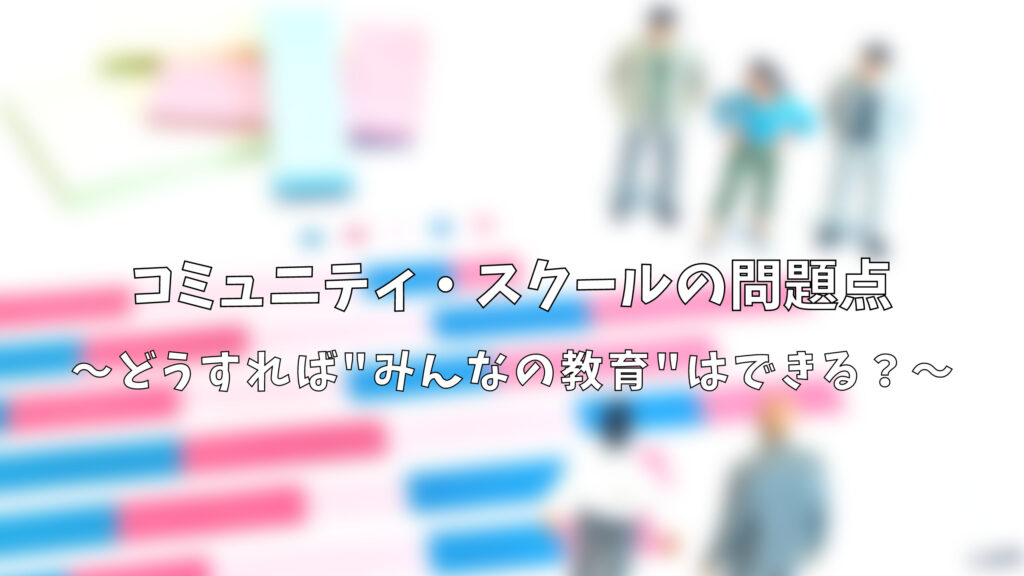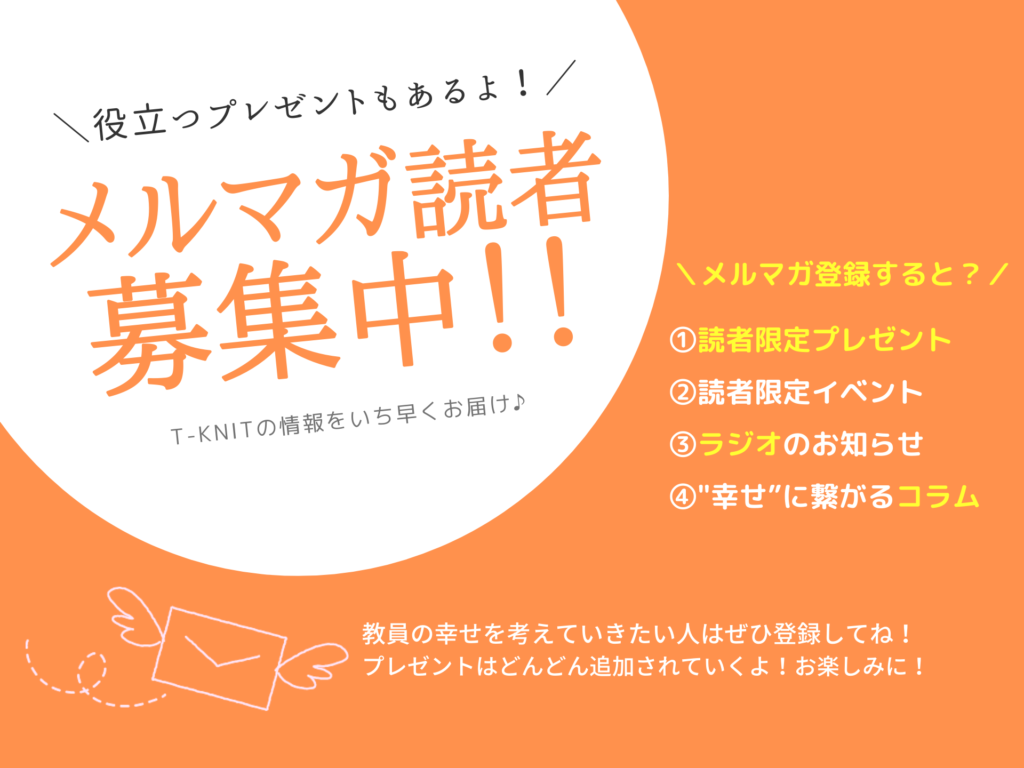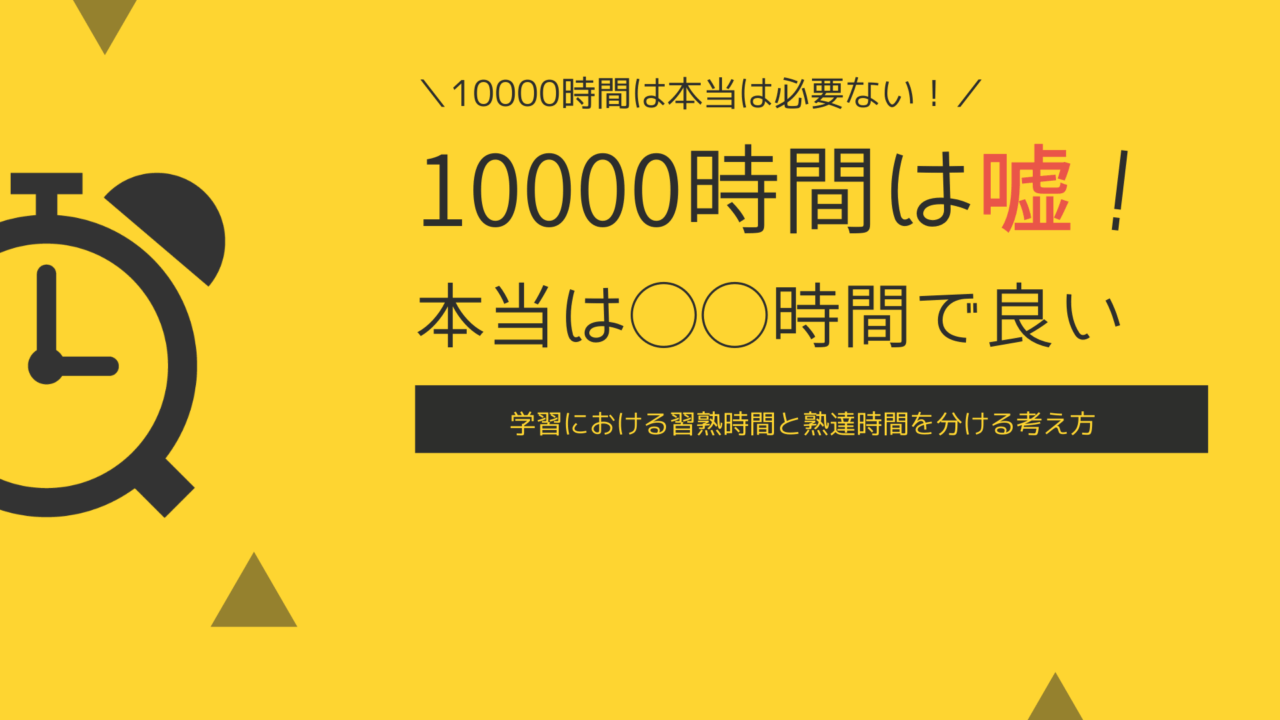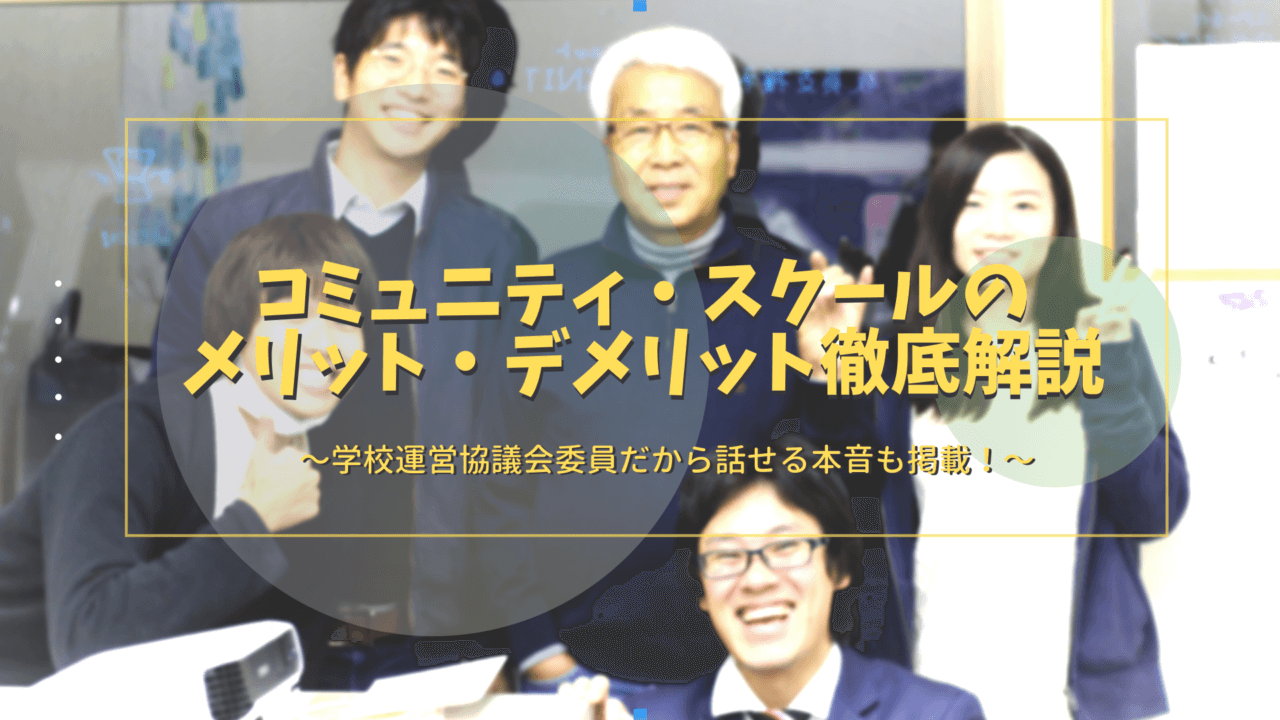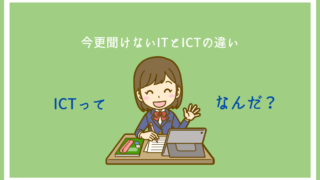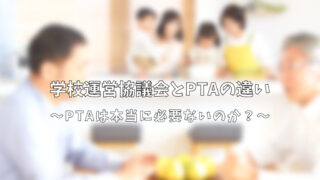今回は質問をいただきましたので、答えていこうと思います。
CSや地域学校協働活動を一体的に5年以上進めていますが、持続可能な状態になっていくための条件整備として、特に力を入れていかなければならない点は、誰のどんな点でしょうか?
40代 女性(生涯学習課)
すでに5年以上進めている…ということは、一定の成果を出せたということでしょうか。
そもそも5年以上継続している時点で素晴らしいと思って構わないと思います。
持続可能な状態にするということは、コミュニティ・スクールで起こる問題点をしっかり把握し、解消し続けている状態であると言えます。
問題点はたくさんありますが、設置初期と設置・継続後で少し異なってきます。
今回はその問題点を知り、持続可能な状態を作るために大事だなと思うことについて、僕自身が見聞きしたり、実体験に基づいたお話をしていきます。
コミュニティ・スクールの設置時に起こる問題点
こちらはコミュニティ・スクールの設置時に起こる問題点です。相当気をつけていないと絶対に起こります。なぜ起こるのか?を知って、対処法を協議していきましょう。
誰が責任を持って進めるのか分からないので学校になりがち
最初、教育委員会から各学校に学校運営協議会が設置されます。この第一回目が学校主導でほぼ行われるハズです。
この時、主導権は学校になってしまいがちで、二回目も三回目も…となってしまいがち。
しかし、学校は忙しすぎるのです。コミュニティ・スクールを理解する間もなく、始めているケースが多く、この主導権を渡せないままズルズルと学校が継続することになり、運営がおざなりになります。
対処法としては学校運営協議会の初期は教育委員会が力を入れてサポートするようにしていきましょう。

なるべく学校が運営する形態から離していくのがポイントです。
地域も、学校の先生も、家庭も、実はコミュニティ・スクールがよく分かっていない
このコミュニティ・スクール自体がよく知られていないため、勘違いしている人、知らない人が圧倒的多数です。
しかも、コミュニティ・スクールは2017年に変更が加わりました。
実は学校教育にそんなに関わっていない地域・家庭だけでなく、学校の先生や、行政もコミュニティ・スクールを理解していないということが多いのです。
対処法として、できれば設置前にCSマイスターを活用し、コミュニティ・スクールの理解を深めていきましょう。
CSマイスターは設置前であれば研修費用を国が負担してくれます。(その年の予算によって変わると思うので、要確認です)
設置後だと教育委員会の負担になるケースが多いのです。
ただの学校支援ボランティアの集まりだと思ってしまう
コミュニティ・スクールと聞いた時、「学校応援団を作ろう!」という動きが加速します。なぜなら学校は忙しく、大変だからです。
しかし、作ること自体は間違いではないですが、大きな間違いを起こしていることにみんな気付きません。
学校として大事な軸を決めず学校支援ボランティアを集めてしまうと、コミュニティ・スクールが単なるボランティア活動の場になってしまい、コミュニティ・スクールの目的と大きく外れることになります。
なぜボランティアを募るのか?どんな学校にしたいか?どんな子どもたちを育みたいのか?を協議することがとても大切です。
協議の場を学校評価の場にしてしまう
学校が主導することになりがちな学校運営協議会。その一番の弊害は進め方が分かっていないということ。
よくあるパターンは、どんなポイントに注目してもらいたいか分からないまま授業参観をさせ、学校資料の読み合わせをし、学校はいかがでしたか?と評価を促して会を終わりにさせる。

これだけで正しい学校評価ができる人なんていませんよ!
このような評価の場自体が学校運営協議会として微妙な進め方で、大事なのは協議すること。
集まったみんながどのように学校を考え、未来を想っているのか?その弊害は何なのか?これを話し合いながら、一番大事な軸を見つけ出していくことなのです。
協議の場ではファシリテーターを置くことが重要になります。全員になるべく平等な発言機会を与えていきましょう。
事例から真似しようとして失敗する
どんな学校にしていくか?より、何をするかをいきなり話し合うことが多いです。
これは僕自身がやってしまったのですが、「大事なのは挨拶運動!」という声を聞いて、他県の取り組みを持ってきて、進めて、結局トラブルがあったから何もしない…という結果に終わりました。
なぜ途中で終わってしまったのか?というと、その事例はなぜ大事なのか?本当にやるべきなのか?何を自分たちは大切にしているのか?という目的が決まっていないまま事例をやることが先になってしまったからです。
つまり、手段の目的化が起こってしまった。そうなると、何かしらの障害が起こるとそれを理由にやらなくなってしまうのです。
大事なのはまず自分たちが何を大事にしていくか?という目的を協議していくことが先でしょう。
集まる回数が少なすぎて全然進まない
学校運営協議会の集まりは一般的に年4回しか集まりません。
しかし、学校運営に関わる重大な会議を何の工夫もなく年4回で何とかすることはまず難しいでしょう。
なぜなら、3ヶ月ごとに集まったりするので、前回話した内容をほとんど忘れてしまうからです。とにかくスピード感がなく、一度話したことがなかったことになり、0に戻ってしまうということが往々にしてあります。
- Slack、LINEWORKS、サークルスクエアなどグループウェアの導入を行なう
- 単純に集まる回数を増やす
- 議事録をしっかり残し、何が決まったのか?途中になっているものはなにか?を工夫しながら書き残す
このような会議以外の準備・継続の工夫を考えていくことがとても大事になるでしょう。
堅すぎて本音が言いづらい
活動は緩くやっていても、会議・協議の場になると途端に堅くなるということが多いです。
考えられることとしては「なにかを決めなければならない」という意識を持ちすぎてしまっているかもしれませんし、やる気のある委員とやる気のない委員の温度差が「こんなの言って大丈夫かな」という空気を生み出してしまうこともあります。
また、「なにかないか?」など一方的に答えを求められる場面を作ることがあり、「なにか気の利いたことを言わなければ…」と知識の無さを辱めるシーンを生み出しているケースに気づかないこともあります。

本当に小さなことですが、会議の堅さは事前の人間関係構築、目的共有ができているかどうかで大きく変わってくると思います。
大事なのは本音を言って、どうしたら子どもたちのためになるのか?を話し合うこと。それができていないなら会議・協議のリ・デザインが必要です。
ファシリテーターを用意するなど、協議の場をスムーズに進行する工夫を行いましょう。
お互いに連絡が取れない状態が続く
ここが大きな課題点なのですが、学校運営協議会として集まった方々はなぜか最初、気軽に連絡を取りあいません。名刺は交換するのですが、その後、やり取りをしなかったりするケースが非常に多いのです。
この連絡が取れない・取らない状態を続けると会議の場が見知らぬ人同士の話し合いになります。それはとても話しにくいでしょう。
ここで大事なのは連絡先を交換し、知り合いに。知り合いから友達になっていくことです。
一番使っているツールとして、やはりLINEが挙げられるので、確実に連絡先を交換し、グループを作っておきましょう。

集まった初日、コーディネーターとなる人が会議終わりに「LINE交換しましょうよ!連絡取りあいたいですし」と言えば、結構すんなりLINE交換してくれます。そのあと、ちゃんと連絡取り合うことが大事です。
学校運営協議会は年配、シニアの方が抜擢されるケースが多くあります。この場合、LINEはほぼ使えず、メールもあまり読まないという方が多いので連絡が取りづらいです。
どうしたら連絡取れるようになるか…コーディネーター(地域学校協働活動推進員や、教育委員会、委員の中で率先して動く人)の役割が重要になるでしょう。
コミュニティ・スクールをしばらく運営した後に起こる問題点
コミュニティ・スクールは設置したあとも順風満帆ではありません。
学校運営協議会、地域学校協働本部はコミュニティであり、いろんなコミュニティ的失敗事例が起こります。参考にして、少しでもリスクを軽減していきましょう。
方向性の違いでトラブルが起こる
学校運営協議会を続けると、ケンカのような一触即発の空気になったり、表に見えない陰湿ないじめが発生するケースがあります。
これは方向性の違いが生み出しているものであり、何のためにの共通認識がズレて、その人個人の大切にしているアイデンティティを汚している可能性があります。
解決法として、1 on 1の個人面談を行ったり、会自体のグランドデザインの見直しをしていきましょう。

ここで文句を言う人は学校運営協議会とはなにかを知らない人も多いため、明らかに間違っていた場合は「ここはそういう場ではありません」とハッキリ伝えて、残るかどうか相手に決めさせましょう。
組織を脈のない人材バンクにしようとする
これは地域学校協働本部でありがちなケースですが、人数を集めることを重視しすぎて脈のない人材バンクが出来上がってしまうことがあります。
この脈のない人材バンクは負の遺産そのもので、役に立たないどころか、大きく管理コストがかかるため、学校の働き方改革とは真逆の方向性に行くことになります。
- 人材バンクを作り、登録後、しばらく連絡しないと連絡が取れなくなってしまう
- 年数が経過すると状況が変わるので、情報更新が必要になってしまう
- 誰も親しい人がいない状態になると、連絡するのにパワーを使う
- 一旦作ってしまった場合、ずっと管理継続することを要求され、切り離せなくなってしまう
- 管理するのが先生になるので、働き方改革にならず、先生の負担を増やしてしまう
人材バンクより、名簿。名簿より人間の絆です。
小さくても良いので、連絡が取り合える人から広げる意識を持つこと。また、名簿を活かすコーディネーターの存在は必須です。作るのなら活かす工夫をすることで脈が動き出します。
コーディネーターがいない
一番の課題と言っても良いのですが、コーディネータを設置しないことが多いです。
こうなると、連絡調整役をメインとする人がいないので、コミュニティの中の誰かになります。この場合、その人のやる気次第…となってしまうので、地域によってバラバラな進み方になるのです。
本当に誰もいない場合、教頭先生にその任が降りてきますが、教頭先生は学校の中にいるし、学校校務で忙しいので、コーディネートできる余力などほとんどありません。
対策としては教育委員会が地域学校協働活動推進員を早く設置することが一番の解決法です。それ以外では、外部委託でアドバイザーに継続支援をお願いするのも手です。
強力なリーダーがいないと何もできないトップダウン組織になっていることがある
コミュニティあるあるですが、強力なリーダーに依存するトップダウン組織になってしまうことがあります。特に最初はリーダーシップが重要なため、この状態になるケースは多いでしょう。
トップダウンは強力な一人のリーダーシップで早く完成するという特徴がありますが、だんだん、「あの人がいれば良いか」という空気感になり、活動がリーダー一人だけになりがちです。
スタート直後はリーダーシップじゃないと動かないケースも多いのですが、一方依存ではなく、相互依存(相互支援関係とも言う)のフラットな関係性を目指していきましょう。
- リーダーの行っている役割を渡す
- 勉強会をし、全員が動くことの大切さを考える
- コーディネーターをリーダー以外に設ける
- ファシリテーターをリーダー以外に設ける
- 渡すからにはリーダーのように完璧にしなくても良い
…など。
前年踏襲をし過ぎて、改善が起こりにくくなる
協議の場にて一番厄介なセリフが「前年度は〜…」という言葉です。
もちろん、前年踏襲という言葉は一度行ったことをルーティン化、システム化するということと同じなので楽に早く実行できるというメリットはあります。
しかし、何のために?がズレていないかはしっかり確認する必要があり、納得感を持って進めないと手段の目的化が起こって、「今年もこれを”やらなきゃいけない”」と言うようになります。
特に大きなイベントはグランドデザインに照らし合わせて、本当にやる必要があるのか?を考えるクセを付けましょう。
動く人と、動かない人の差が不満を生み出す
活動を続けていくと、意識的に動く人と、動かない人の差が生まれてきます。
しかし、これは正直しょうがないと思っています。なぜなら、そのコミュニティだけがその人の居場所ではなく、家庭もあり、仕事もあり、その他の集まりだってあるのが当たり前なのです。

全員が同じ意識で、同じくらい活動するのは洗脳に近い形で、宗教チックなのではないかと思います。活動はしているけど、その人個人の尊重は失われてしまうのではないでしょうか。
コミュニティには働きアリの法則という考え方があり、ほとんどが2:6:2になります。つまり、よく動いてくれる人は全体の2割しかいないということです。これは法則であり、通常であれば避けられないことなのかなと思います。
- 働きアリの法則とは?(詳細はこちらをクリック)
動かない人がいるほうが正常であると認めることが大事。よく動いてくれる2を満足するようにし、たまに来る6を巻き込むキッカケを作っていきましょう!
既存組織の段階的ステップアップや、協働に悩む
コミュニティ・スクールを活性化させる際に課題になっていくのが、既存の組織との共存・統合です。
本来であれば学校運営協議会や、地域学校協働本部は法律で守られ、権限があり、国からの予算が降りてくる組織なので、そちらのほうがメリットが多くあります。
しかし、メリットがあると言っても、それぞれの地域で課題が違うように、組織の扱い方も違うので簡単に導入・移行というわけにはいきません。
特に精力的なPTA本部が動いている場合と、すでにコミュニティ・スクールに似た組織を作ってしまっている場合、移行は難しくなります。
この場合は、新規で立ち上げるというよりは、既存の組織をそのまま学校運営協議会や、地域学校協働本部として成る方法か、既存組織を交えて協議の場を設定していくと良いでしょう。
コミュニティ・スクールの問題点はチャンスでもある
コミュニティ・スクールにはたくさんの問題点がありますが同時にチャンスでもあるということが分かると思います。
- 教育委員会が設置直後はサポートに力を入れる
- CSマイスターを呼んで研修会を行なう
- 何のために?をみんなで考え直す(設置後も大切)
- ファシリテーターを用意し、全員に発言の機会があるようにする
- 会議・協議以外でもコミュニケーションが行えるようにする
- 方向性の違いが起こったら1対1の面談や、何のために?を問い直す
- 地域学校協働活動推進員のようなコーディネーターを用意する
- トップダウンから徐々にフラットな組織へ移行する
- やることよりもやらないことを協議して決める
- 既存組織はそのまま活かす方向へ。無理なら協議して協働できる形へ
これを誰がやるか…?と考えることが多いのですが、組織の最小単位は『あなた』です。
一人ひとりがどこか一つでも良いからできることはないか?と考えて、全員がリーダーシップをとっていくことが大事だと思います。
『あなた』という存在がどのような貢献をし、何ができて、何ができなかったのか?を考えていくこと。
これが全員自然にできるようになった時、それは組織として成熟した状態になっているはずです。
でも、いきなり組織ではなく、あなたがまず何ができるのか?を考える。
これが一番大切なことなのです。