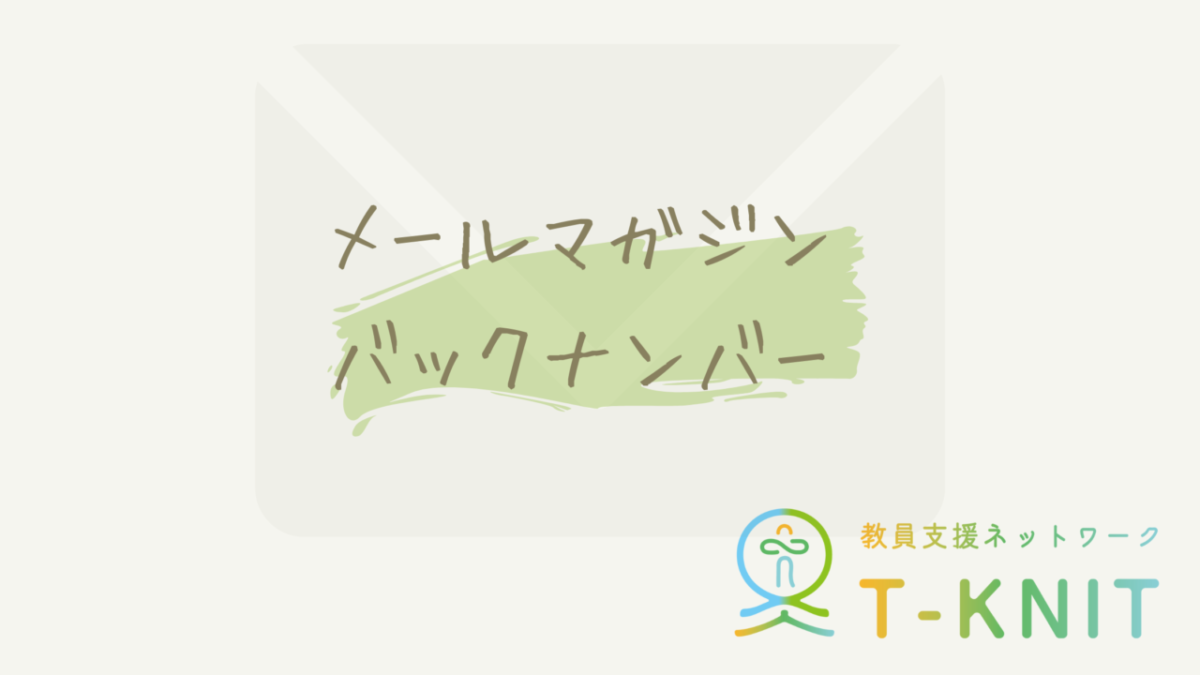こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
ICTの発展などから、学習の個別最適化が多くの場所で扱われるようになり、今ではこの言葉も教育関係者であれば、当たり前のように知っているかと思われます。
この個別最適化の影に隠れるように、たまに出てくるのがこの「自己調整学習」というキーワード。
みなさまは、この「自己調整学習」について考えたことはありますでしょうか?
✏️自己調整学習とは?
読んで字の如く、自分で学習を調整していくことを自己調整学習と言うのかな?と頭に思い浮かべるのではないでしょうか。
まさしくその通りです。
「自己調整学習」は,1990年代からアメリカの教育心理学者,バリー・ジマーマン(Barry Zimmerman)らが中心となって提案している新しい教育心理学の理論体系です。
(SRL研究会参照)
他者に依存せず自律的に学習を進めていく 過程や学習者像を捉えるのが自己調整学習の概念であり、そのためにはいくつかの考慮すべき項目があります。
(日本における自己調整学習とその関連領域における研究の動向と展望 ――学校教育に関する研究を中心に――参照)
- 動機づけ
- 自己覚知に至る過程
- 目標達成の過程
- 環境の影響
- 力の獲得の仕方
個別最適化学習と聞くと、個々に応じた環境や難易度を設定すると言うことにフォーカスしてしまいがちですが、児童生徒がそれぞれ、どのように自走をしていくまで支援するのかに着目する必要があるのです。
📓根本的に学習スタイルが変化する
この「自己調整学習」は文部科学省の資料の中にも提示されているものです。
つまり、当然私たち教育者の教育の形をグレードアップさせて変化させていくのはもちろんのこと、児童生徒の学習スタイルも既存のものから、自走式へとアップデートしていくことが求められているのです。
子どもたちそれぞれが、学習に対して能動的に活動していく。
つまり、これまではただ単純に座って前にいる先生の話を聞いていればよかった学びが、自分で何をどのようにどの程度学んで何を目標にするのかを設定していく必要があるのです。
探究活動や学外活動など、少し普段の教科学習とは異なるところで毎度のように出ていたPDCAサイクルというものが、もはや当たり前にどの時間でも実践していくことが求められるわけです。
とはいうものの、学び方や学校に対するイメージも12年間の間で知らず知らずのうちに染み付いていってしまうものです。
それでもいまだに、チョーク&トークの黒板にベッタリ、ひたすら話し続けるスタイルの授業をする先生もちらほらといます。
🧑🏫学び方を伝える時代に
ICTはもはや端末を入れればいいというだけではなく、AIの活用などにも進んできています。
そんな中で我々教育者のすべきことは、何かを伝える、教えるではなく、学び方を学ばせる、学び方を伝えるということに移行していくのではないでしょうか。
とは言っても、いま教員として働いている多くの人は、これまでのチョーク&トークの授業しか受けてきていません。
しかしだからこそ、いいのではないかなと思うところもあります。
これからの教育のあり方は「先生→生徒」の一方的な指導ではなく、「先生↔︎生徒」の往還関係が必要になってくるわけです。
つまり、生徒の学びのあり方をみて、教員も学び教員の学びを生徒へフィードバックしてというように相乗効果を生むような教育へと変化します。
「生徒へ伝えられることがない」、「どうしよう」、「でも教えなければ」と肩肘を張るのではなく、生徒と同じ目線で学びを実践していく姿勢こそが求められていくのです。