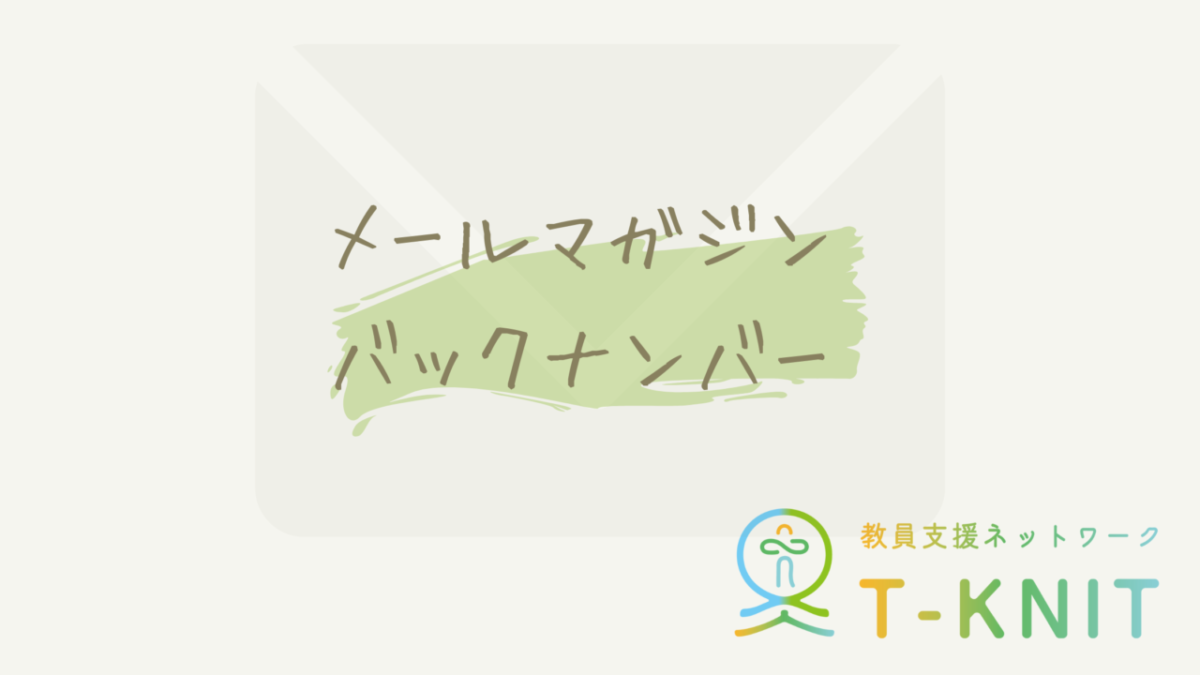こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
5月にネットニュースになった北海道教育委員会の教諭への処罰の問題が、いまだにネット上で物議をかもしております。
内容は児童に注意をした教員が児童に蹴られたとに反射的に蹴り返してしまい、教員だけが減給処分を下されたという内容です。
今日はこの事案について考えていきたいと思います。
⚡暴言、暴力はダメと言いつつも?
学校で必ずと言っていいほどある、児童生徒への言葉遣いの指導。
高校生であれば、いくらかそう言ったことも少なくなるのかもしれませんが、学年が小さければ小さいほど日常茶飯事です。
私も以前まではそこまで感じなかったのですが、職場が変わり最近はこう言った発言を聞く機会が増え、辟易しています。
最近でこそ、少なくなりましたが以前までは教師vs生徒の構図があり、教師への反抗的な態度を取る子も多かったことでしょう。
以前はそれこそ体罰という形で大人から子供への制裁があったと思います。
最近は、各学校にある指導内規のようなもので決まっていることがほとんどではないでしょうか。
保護者召喚や学年主任からの指導、家庭謹慎などさまざまな指導の形態があります。
暴言や暴力はダメと言いつつも、そう言った行為を罰則で防ぐ。
ここに教育的な効果はあるのでしょうか。
暴言や暴力がなぜダメなのか、どうして罰則が与えられるのか、一般的な子どもであれば周知の事実としてわかっているはずですが、おそらく全く分からずに、分かれずに生きている子もたくさんいるかと思います。
🧑🤝🧑子どもと大人の学校での関係は?
子どもも一人の人間として教育が必要。
こんなことをよく耳にします。
確かにその通りだと私も思います。
ただし、だからと言って立場も同じというわけにはいきません。
だからこそ、今回の案件も教員が児童を蹴ったという部分だけがピックアップされてしまうわけです。
当然、一人一人の教育力も必要になるかと思います。
言葉での解決ができず、先に暴力が出てしまう子どもというのはたくさんいます。
そう言った子どもに対して我々大人側も、個々にあった対応が必要になることでしょう。
ただ、場合によっては50人近い大人数を一人で指導する教員にとって、それは難しい話です。
理想は1対1❌50でしょうが、1対50にならざるを得ないのです。
🌫️教育にも上下の関係が必要なのか?
子どもを尊重することは大事です。
ただし、だからと言って子どもを一人の人間として、認めるのは違うのではないかなと最近は思っています。
どうしても人それぞれ特性があって、子どもはまだその特性と自分自身が向き合う準備ができなていないことがほとんどです。
ともなれば、子ども以上に長く生きていて自分との向き合い方もわかっている大人が、そう言った視座から物事を伝えていくことは必要なのではないでしょうか。
教師は指導するのではなく伴走者。
教科学習や自走する力の持つ子どもにとってはそれが最適解だと思います。
ただ、自走するレールも分からない子どもがいたとき、果たして伴奏者としているだけで十分なのでしょうか。
教育の正解はないとはいえ、今回の案件も過剰に教員が聖職者としての仮面を強要されているような気がします。
教員も一人の人間であり、感情があります。その上で聖職者としての職務を全うするためには、上下の関係は必要なものになるのではないかなと思います。