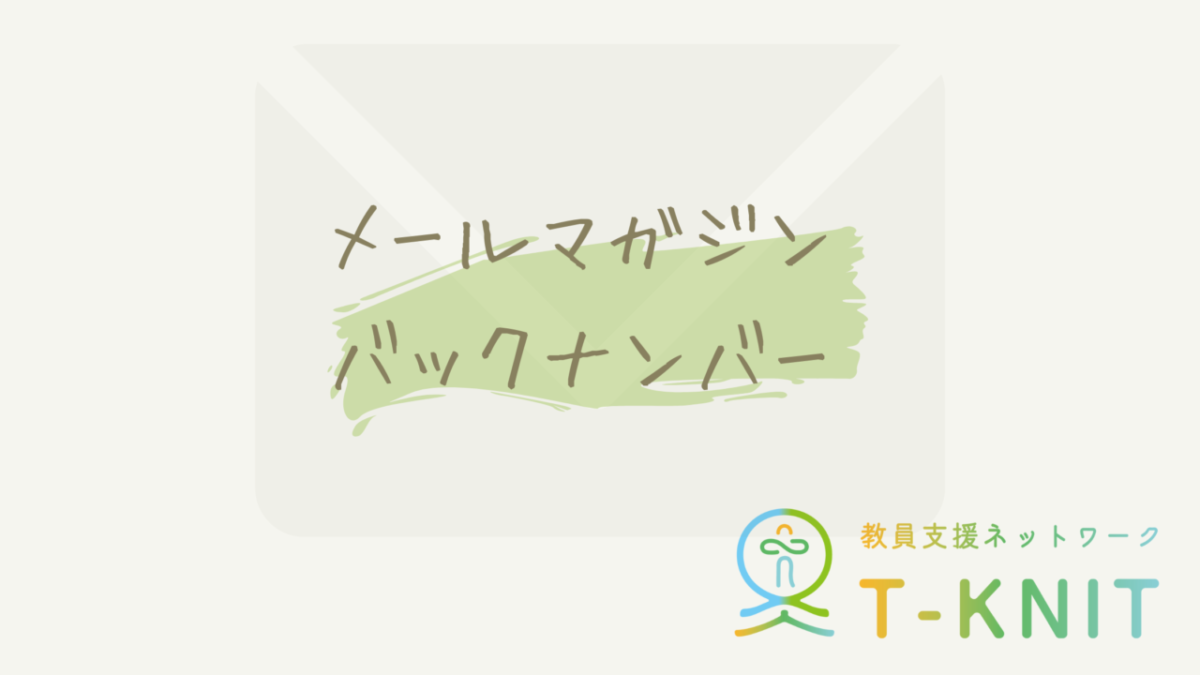こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
今年は戦後80年。
毎年のことではあると思いますが、8月の6日と9日を過ぎ、この1週間、今年はよりこのフレーズを多く耳にしたのではないでしょうか?
とはいうものの、そんな戦時中とはかけ離れた生活をできている現代。
平和教育はどのように行っていくべきなのでしょうか?
🏫学校の中で行われている平和教育は?
令和7年8月8日に行われたあべ文部科学大臣の記者会見では、平和教育について発言される時間がありました。
教育においては、各科目での学習はもちろんのこと、戦争体験者の減少と高齢化が進むことを問題視していました。
こういった方々の声を録音したデジタル教材の活用など持続可能な形での平和教育の充実を目指すとのことでした。
各学校での平和教育はどのように行わているでしょうか?
私が以前勤めていた学校では、原爆投下日に合わせて黙とうをするよう全校放送で流れたり、礼拝の中でお話があるという程度でした。
学校のカリキュラムはそれぞれのため、まったく触れないというところはないにしても、平和教育に対する比重を高く設定している学校は少ないのではないでしょうか。
歴史として知っているという人は多いにしても、この平和教育に対してどこまで踏み込んで考えるべきなのかは学校ごとに任されている部分があります。
🕊「平和」とは?
では、「平和」という言葉を考えたときに、それがどういうことなのかを説明できる人は、果たしてどれくらいいるのでしょうか?
おそらく教員も生徒も保護者も含めて、それぞれがそれぞれの答えを持っていると思います。もしくは、まだ持っていない、考えたこともないという人もいるでしょう。
そして明確な答えや確信を持たないままに卒業していく人がほとんどです。
かく言う私もそれを誰かに伝えられるかと言われると難しいところがあるかもしれません。
でも、だからこそここに平和教育の意味があるのではないでしょうか。
これまでは、人から人へと伝えることで感情や思い、背景も含めてリアルに伝わっていたところがありました。
しかし今は、インターネットを調べればすぐに情報が出てきて、戦争や平和を知った気になれるわけです。
そこには事実しかないのに。
哲学的ではあるかもしれませんが、平和教育とはその事実を知るだけではなく、その事実から自分なりの答えを導き出すところにあるのではないでしょうか。
🔎より難しくなる?
どんなに戦争体験者の声をデジタル化したところで、リアルに聞く話には勝てません。
デジタル化をしてしまった瞬間に、それは実際にいる人ではなくて、いた人やいるかもしれない人になってしまうのです。
平和を考える以前に、事実そのものをインプットすること自体のハードルが上がってくるわけです。
平和教育はより難しくなっていきます。
ただ、ここまで日本の戦争について考えての平和教育について書いてきましたが、平和教育で注目すべきは日本だけではありません。
世界を見れば、今だに戦争が続いているところも多くあります。
また、日本とも状況や環境が大きく異なるわけです。
でもだからこそ、そういった現状でしか聞けない話を体験として捉えて、それと同時に日本の歴史についても学んでいく。
そしてそれらを伝承していく。そこに平和教育があるのではないでしょうか。
昨年の暮れにある関わりから招待していただき、沖縄に平和学習に行きました。
沖縄の現状やそこに住んでいる人の話を聞いて、日本の戦争はまだ終わっていないんだなと深い気付きを得られました。
実際に聞かないと分からない学びや事実、いくらでもあるからこそ、平和教育の在り方を教員側がしっかりとマネジメントしないといけないと深く感じました。