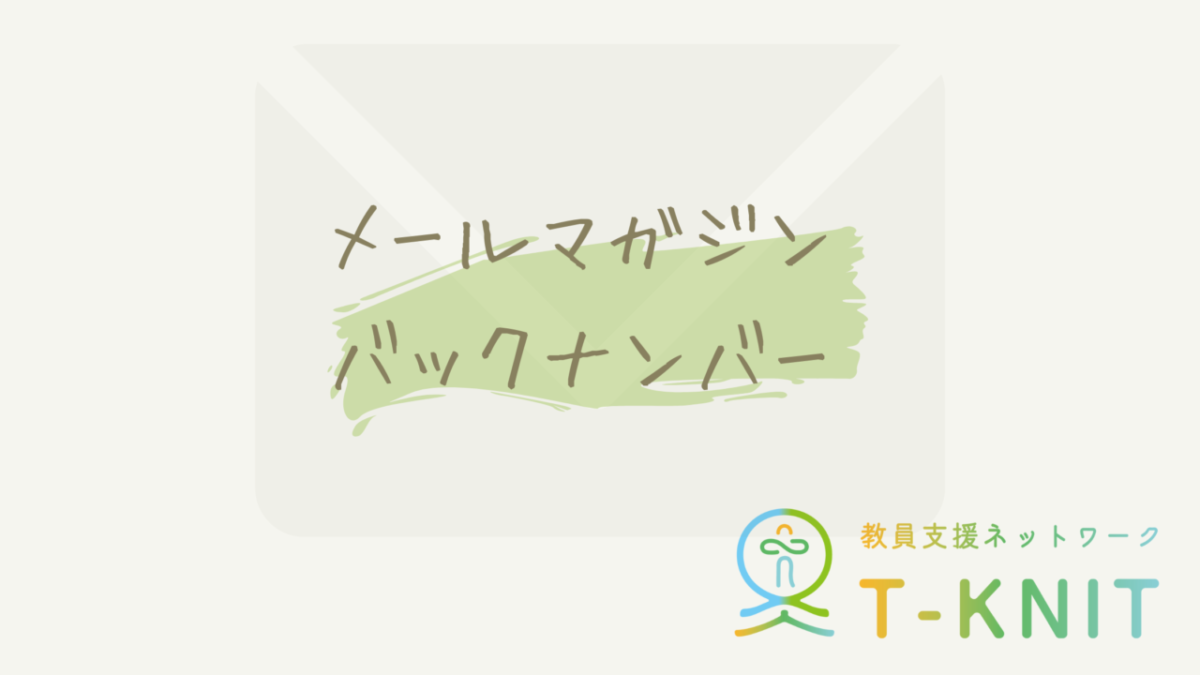こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
今日もまた次期学習指導要領について考えていきましょう。
昨日、中央教育審議会の教育課程企画特別部会から次期学習指導要領改訂に向けての論点整理という資料が提示されました。
(https://www.mext.go.jp/content/20250925-mxt_kyoiku02-000045057_01.pdf)
文量は多いですが、ぜひ流し読みでもいいので見てみると、これからの教育として国が求めている方針が見えてきます。
🔺基本的な方針は?
次期指導要領では、3つの方向性として下記項目を打ち出しているようです。
①「主体的・対話的で深い学び」の実装(Excellence)
②多様性の包摂(Equity)
③実現可能性の確保(Feasibility)
うーん、なんというか実に現代的、、、。と私は感じました。
皆さんはどのように感じられたでしょうか?
この資料の中ではさまざまな観点からこの3つを説明してありました。
私としては、これらを学習指導要領に盛り込むとなると非常に難しいのでは?という実感があります。
評価軸が変わるかは、まだ分かりませんが、今の指導要領の「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」でさえ、先生の頭を悩ませていると良く聞きます。
「主体的に学習に取り組む態度」を評価するのに、どうすればいいのかという点、ここはまだ現場の中でも定まっていないように感じます。
果たして、それは主観でいいのか、客観的に評価するとしたらどのようにすればいいのか、そもそも評価していいものなのか。
あえて批評的に、そして表面的に捉えたことで考えますが、これまた抽象的になりすぎて現場の先生たちは頭を抱えるのでは?と感じました。
🔑深い学びはそのままに
これ、「知識・技能」、「思考・判断・表現」の評価軸がなくなるのでは?と予想したのにも理由があります。
この資料を読んでいると、なんだか「主体的に学習に取り組む態度」や「深い学び」がエコ贔屓されているように感じるのです笑。
「知識・技能」も「思考・判断・表現」もあくまで深い学びのために必要なスキル的側面というように捉えられます。
批判ではないですが、文部科学省は基本的にこれまでの学習指導要領を否定するようなことはしません。
あくまでも、“改訂”。時代に合わせて進歩させたというような書き方をします。
実際、教育に絶対的な正解はないので、それでいいとは思うのですが、今回の改訂ではなんとなく、これまでの詰め込み型学習の正当化をしているようにも感じたわけです。
かつてどこの学校説明会に行ってもそのそのワードを耳にしないことはないほど、一世を風靡していた「アクティブラーニング」という死語もその一例。
「知識・技能」、「思考・判断・表現」だって、実は深い学びを促進するためのものだよと言わんばかりの雰囲気です。
とはいえ、この方針に私は賛成です。
もちろん教科学習も大事ですが、それ以上に1体1の人としての向き合い方や、自ら自走する力をつけていくことにこそ意味があるのではと思うからです。
🗒️変わる学び方に入試制度はどのように対応するのか?
正直、ここまで大きく舵をきった改訂に驚いています。
私の中ではいい教育だなと感じるのですが、今の社会の制度に合っていないようにも感じるのです。
授業時数や時間の精査、自由度をつけた内容の編成、さまざま学校の中でこういった力をつけていくための対策は取れそうな気はしますが、それでも大学入試の制度はそこに追いつけていません。
どうしたって、中高生からすれば大学への進学、いい会社への入社がいまだにベストな進路として根強く印象残っているように感じます。
次期指導要領に真面目に取り組んでいる学校こそ、そこの矛盾は、これから先もっと大きくなっていくように感じます。
総合型選抜の増加が増えてはいるものの、まだまだ大学入試もそこまで大きく変化はしていません。
大学や会社、社会としても、特別な活動をしている自己表現ができるという学生と、必死に試験勉強をしてきて偏差値を上げてきた学生の差を明確化できるほどのシステムはないように感じます。
もちろん、どちらも違った力を持っています。
この社会と結びつくためのバランスこそが今後の教育の課題になっていくのかなと思います。
皆さんはどのように感じますか?