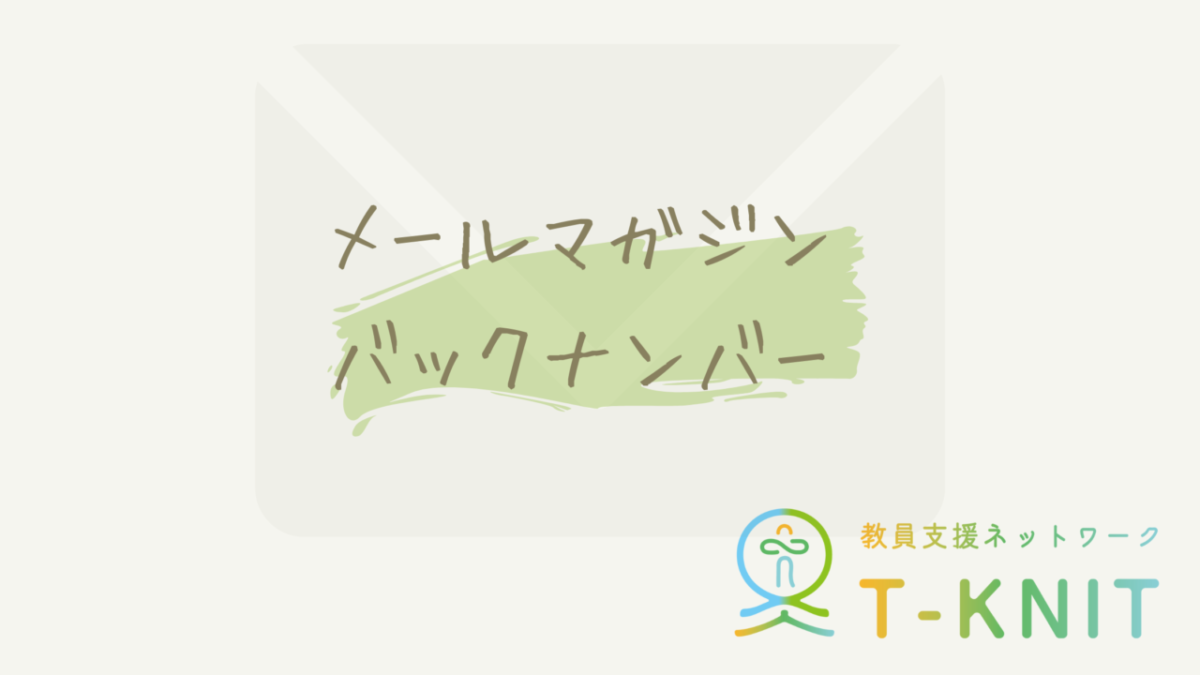こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
学校にある掃除の時間、皆さんはどのようにお過ごしでしょうか?
学校によっては黙掃の時間にしたりと、意味合いを持たせているところもあるのではないでしょうか
今日はそんな掃除の時間について考えます。
🧹なぜ掃除?
日本人の学校では当たり前となっている掃除の時間ですが、海外の事情などを確認すると意外と事例としては少ない方なのです。
では、なぜ日本の学校にはずっと掃除という文化が残っていたのでしょうか。
これは武道から来ていると言われています。
仏教や各武道などが盛んだった日本では、自然とそこで行われていた掃除の文化が学校にも浸透していったわけです。
場をきれいに保つこと、これこそが学びや武道の第1歩だと考えられてきたわけです。
それ以降、生徒への罰則として掃除が使われたり、協調性の醸成などとしても掃除の時間は有効と考えられて、学校の中での当たり前になっていったわけです。
学校中全てを掃除する学校こそ少ないものの、自分たちの教室の掃除は、そのクラスで行うところが多いと思います。
☁️環境の乱れが心の乱れ
私自身、教育業につくかつかないかくらいの頃、よくこの言葉を聞きました。
環境の乱れが心の乱れ。
教室が汚ければ汚いほど、そのクラスの雰囲気も荒れていくといったものです。
相関性があるかどうかは分かりませんが、よく聞く言葉です。
確かに、荒れているクラスがきれいな状態で保たれているという状況はなかなか考えにくいです。
私自身、そのようなクラスには出会ったことがありません。
大抵、荒れているクラスはそれ相応に教室も汚いことが多いです。
だからこそ、教室はきれいにしようと心がけています。
⏰掃除の時間は必要かどうか
では、掃除の時間は必要なのでしょうか。
日本の伝統と文化としての掃除という教育活動は、海外からも称賛されています。
評価されているから必要というわけではないのですが、私は掃除の時間は必要かなと思っています。
一つは、やはり教室をきれいに保つため。
清掃員さんを呼んで教室を掃除してもらうというのは簡単かもしれません。
自分の学ぶ空間を自身できれいにするという点が、子どもの教育においても家庭教育から一貫した学びとして必要だと思うからです。
二つ目に、コミュニケーションの部分。
これは生徒同士のコミュニケーションだけでなく、生徒と大人のコミュニケーション。
掃除の時間を通して、自然と担任と生徒もコミュニケーションをとって、小さな会話を増やすことができるからです。
そう考えると、以前からある掃除も教育の一部として重要なものと考えられますね。