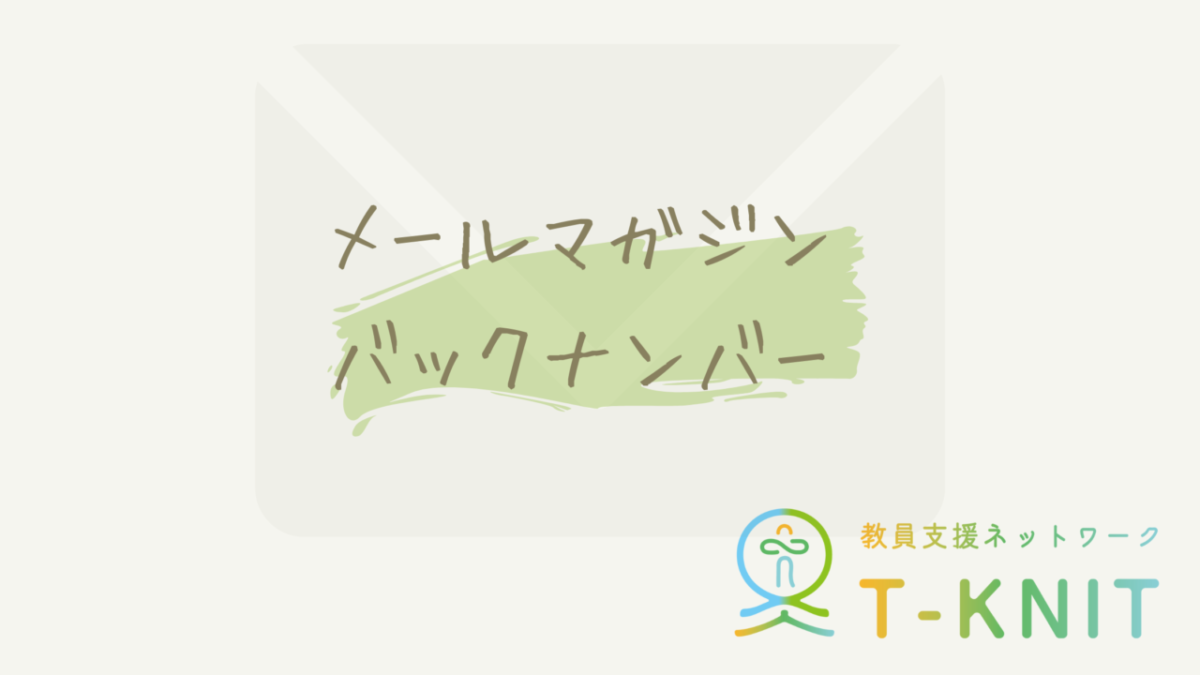こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
皆さんはご自分の教材研究を行ううえで、どの程度学習指導要領を踏まえた形をとっているでしょうか?
おそらく検定外教科書を利用せず、普通の教科書を利用している限りはほぼ100%学習指導要領の意向に沿って授業を行っていると言えるかと思います。
今日はそこに疑問を呈している動画を1本紹介します。
🏫現行の学習指導要領体制のままでは日本の教育はよくならない?
ダイジェスト版ですが、面白い動画がありました。
タイトルに惹かれて見てみましたが、納得する部分もあり共感できました。
簡単に要約をすると、名古屋大学名誉教授の植田 健男 (うえだ たけお)さんが、下記のようなことをお話しされています。
本来、学習指導要領は子どもの実態に合わせて柔軟に変化しながら利用していく手引きのようなものであった。
しかし、いつからかそれが法的拘束力を持つようになり、すべての教育機関がこの学習指導要領という定められた中で教鞭をとっている。
一定のレールが敷かれた学習の中で地域や実態に合わせた教育を行っていくことができるのか、その根本を考えた方がいい。
私も学習指導要領の在り方については、大学時代から疑問を抱きながら指導案を作成していたので、しっくりくるものがありました。
ただ、統一して必要な知識をすべての子どもにということを考えると、ある程度の拘束力も必要な気がします。
皆さんはどのようにお考えでしょうか?
📚義務教育の在り方も考える必要が?
先日、テレビでフジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』を見ました。
たまたま、その時に放映されていたのが、『われら百姓家族』という回。
文明の利器をほぼすべて放棄し、山の中で過ごす暮らしを選んだ家族の物語です。
子どもたちは義務教育課程でありながら、家庭の仕事をこなすためにほとんど学校には行かずという状況だったようです。
その子らが大人になったうえで受けていたインタビューを見ました。
成人した今、「馬鹿にされる」、「職業選択の上で不利になる」という理由から高卒認定試験の勉強をしていました。
山の中で過ごす暮らしは、確かにそこでしか得られないものもたくさんあるはずです。
しかし、一方で零れ落ちてしまっている者もあるかもしれません。
この例は極端かもしれませんが、指導要領で定められた範囲内で大学入試が行われている、偏差値が設定されているという現状、これらを学ばないというのは不利を被る選択になっているのかもしれません。
🎓何のために学ぶのか
では、子どもたちは何のために学ぶのか。
私たち教職者は何のために学ばせているのか。
それは、広く言えば世界のため、個人的に言えば生きるため、細分化すれば個の在り方のため。
他にももっとあるのかもしれません。
ただ、日本の学習指導要領ではここが抜け落ちているのでは?と、ここ最近考えています。
果たして、子どもたちの「なんで勉強するの?」という好奇心に、満足させられるだけの答えを持つ教職者はどれほどいるのでしょうか。
私も全員が全員に答えられる自信はありません。
ただ、だからこそ、これらを子どもたちと共に考え、学び続ける関係性がこれからの学校では求められるのではないでしょうか。
新学習指導要領では、既存のものよりも自由度が少し増します。
この自由度の幅の中でどのような教育ができるかがカギになりますね。