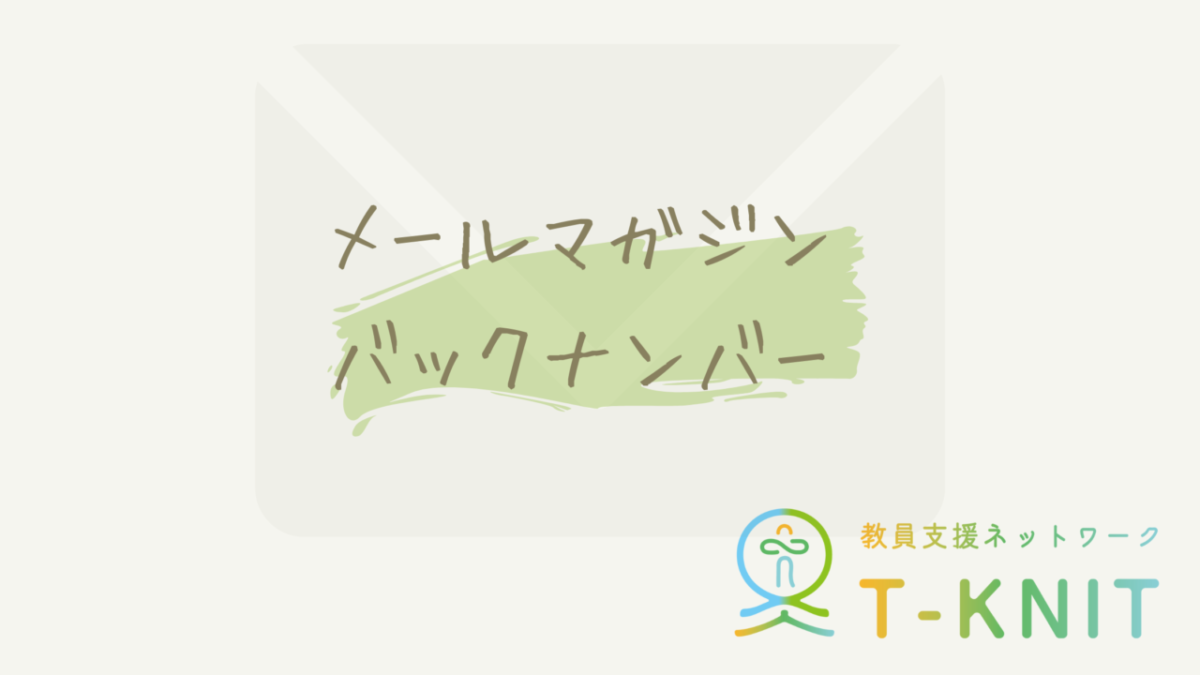こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
一般選抜受験を控える世の中の高校3年生は、追い込み時期の真っただ中です。
私は今年高3を担当しているので、そんな生徒の授業を見ているのですが、実にさまざまな子たちがいます。
今日はそんな高3の受験と普段の授業について考えていきます。
👩🏫受験勉強=授業?
高3の授業になってくると、科目範囲も大体終了しておりほとんどの科目で入試問題演習になってきます。
高3の子からすると、受験勉強に直結するような内容ですので、時間の使い方としてはいいのかもしれませんが、果たしてこれを授業と呼べるのでしょうか。
皆さんにとって授業とは何でしょうか?
これは授業という時間と空間の本質を問うような質問だと思います。
業を授けると書いて授業と呼びます。
確かに一般選抜に向けての挑み方は、どちらかというと技を授けるに近いような気がします。
科目としての面白みや深みを伝えるところまでは言及せずに、よくある入試問題を解くための作法を覚えていく作業。
これは、よく言われる出口指導。
大学へ合格するための授業になっているわけです。
それもある一定の層には需要があるのかもしれませんが、私にとっては授業とは呼び難いとも感じてしまう部分があります。
現に私もそういった授業をしてしまっているところなのですが。
👨👩👧👦『受験勉強は団体戦』は担任力による
よく、受験勉強は団体戦という言葉を聞きます。
私自身もこの言葉は好きで、高3担任になった際にはこの姿勢でクラス経営をしていこうと考えていました。
しかし、思っている以上にこの考え方は難しいと感じているのも事実です。
生徒の中には、一般選抜受験をせずに総合型選抜や公募制推薦、神奈川大の給費制入試などで合格を決めていく場合もあり、時期も方法もバラバラです。
そうなると、何か一つの目標に向かって全員で頑張っていきましょうという気運を作り出すのは難しく、完全に担任の力次第になってきてしまうのではないかとも思います。
推薦組は早くに進路を定めて、浮かれ気分。
一方受験組は秋頃は少し失速するシーズンで推薦組が忙しそうにしているのなんて知ったこっちゃない。
そういった頑張るタイミングの違う中で、お互いにお互いの足を引っ張らずに頑張り切るようなクラス作りは本当に難しいなと感じている日々です。
ただ、だからこその受験勉強は団体戦というのがよく理解できました。
👀受験勉強に勉強の楽しさは見いだせる?
この高3の授業や学習を通してずっと思っているのは、この学習の中に学ぶということへの楽しさというのは見出せるのかというところが疑問に感じます。
学問の楽しみというのは知らないことを知るという探究心と、知りたいという本能的欲求をクリアしていくところにあると思います。
私は物理が好きで物理の教員になったので、それを教えるために学問を深く学んでいくというところに関してはとても得をしていると思います。
しかし、生徒全員がそういうわけでもありません。
物理への興味や関心は私の10%にも届かないかもしれません。
そういった生徒に対して、そこを刺激するような授業をしたいというのが私の理想なのですが、どうしても出口が見えてきてしまうと、そこに向けての指導、そして生徒自身もそこに向けての学びになってしまうというのは避けられないことです。
この出口指導過多になってしまっている高3の授業をなんとかして作っていくことはできないのかなとここ最近はずっと考えています。
皆さんはどのようにお考えでしょうか?