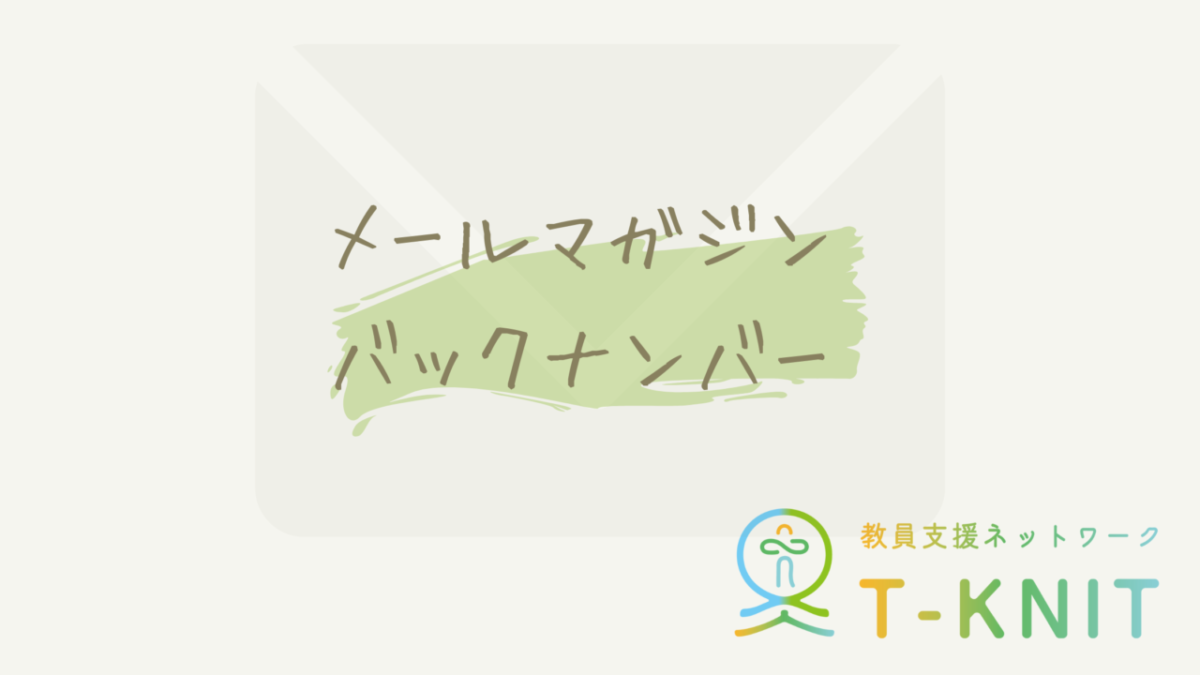こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
学習指導要領改訂の動きが見え始めて、この中身についてさまざまな場面で議論されたり考察されたりする機会が増えてきました。
個人的にはこのタイミングでの改定は早いようにも感じますが、時代の流れを考えると当然のスピード感なのでしょうか。
そんな中、「はどめ規定」の撤廃についての署名活動が行われ始めているようです。
今日はこの「はどめ規定」について考えていきましょう。
🙅♂️はどめ規定とは?
皆さんは、はどめ規定をご存じでしょうか?
学習指導要領の「内容の取扱い」において、当該内容を扱うことを前提にした上で、その扱い方を制限する規定が一般に「はどめ規定」と呼ばれている。
性教育におけるはどめ規定とは、「小中学校で性交を扱ってはいけない」と解釈できてしまう規定のことを指します。
現在の学習指導要領では、小5の理科に「人の受精に至る過程は取り扱わないものとする」、中学校の保健体育に「妊娠の経過は取り扱わないものとする」と記載されています。
この表記があるので、学校現場では性交について教えてはいけない、教えない方がいいという解釈をし、性教育の指導の中でも触れる機会がないことも多いのです。
実際、文部科学省ははどめ規定について、全ての児童生徒に共通で指導をするべきないようではないとしつつも、指導をしてはいけないとは言っていないわけです。
学校や児童生徒の状況に応じて臨機応変に発展的内容を取り扱うことに対しては肯定的です。
ただ、そうは言ってもなかなかプラスαで学習をするというのは難しいものでしょう。
自治体によっては、はっきりと「扱わないでください。」公言しているところもあるようです。
⤴️はどめ規定撤廃で性教育は良くなる?
今回の署名活動は、教員や教育関係者、専門家で構成されている団体がオンラインでこのはどめ規定の撤廃を求める署名を行なっているようです。
では、このはどめ規定がなくなり、学校現場で性教育を教員の思うままにできるとなった時、果たして性教育は良くなるのでしょうか?
正直なところ、私には今とあまり変わらないのではないかという気もしています。
性教育に対する充実を声を大きくして唱える教員も少ないように感じるからです。
2009年にはユネスコから「包括的性教育(Comprehensive Sexuality Education)」という概念が掲げられ、8つのキーワードの中で指導を行なっていくということが提示されました。
「知ってはいるものの、どのように?」
となる先生が多いのではないでしょうか。
大事大事とは言いつつも、学校の中での重要度は行事や試験などより下、何か問題が起きたときに改めて見直されるという程度になってしまっているのが現状です。
👫性教育に出る差、文化的背景の違い?
だから、性教育をしなくて良いというわけではなく、そもそもの日本に合う性教育を考える必要がある気がします。
教科の中で学ぶ性教育は、結局のところ知識重視で現実味のないものも多く、自分ごととして捉えられないものになっているのではないでしょうか。
自分の身体のことについて考えたり、話したり、相談したりするはずである家庭での性に対する関わりが希薄な文化の中で、いくら学校で学んだとしてもという気がします。
オランダやフィンランドでは性教育といったくくりはあるものの、それ以上に生活全体の中で個人の意思や思考が尊重される風土が成形されています。
まずは、家庭でどのように学んで下地を作っていくのか、そして、こう言ったパーソナルなことを公の場所で話せるという安心感も必要になります。
性教育以前に学校で人と人とのつながりを学んでいくという文化を醸成していくことが大事になるのでしょう。
みなさんはどのようにお考えになりますか?