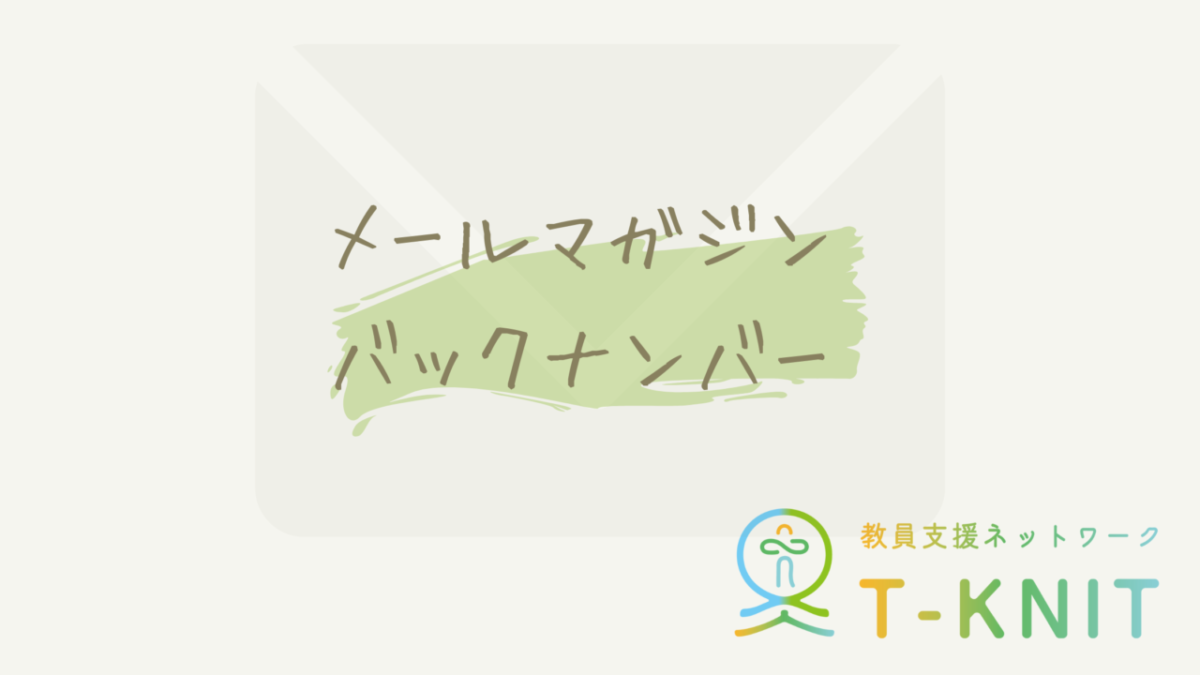こんばんは。
教員支援ネットワーク T-KNITのいがぐりです。
普段は私立の中高教員をしており、個人でもブログを書いております。
よろしければ、ご覧ください。
最近の教育界ではICTを通り過ぎて、すでにAIの教育参入が加速的に動き出しています。
私も最近は課題の評価や成績のコメント、探求の問い出しや業務代行と多くの仕事をAIに任せる時間が出てきています。
もちろん、AIが出した回答は責任を持って全て確認しています。
「若手なんだからそういうのに長けているでしょ?」と思いきや実はそうでもないようなのです。
💻教職過程の学生、ICT実践中?
中高と比較にならないくらい、大学のICT環境も十分に整っているところがほとんどです。
スクリーンやプロジェクターなんてのは当然。最近ではGoogleクラスルームも利用して、よりスムーズに課題のやり取りなんかもしています。
そのため、教職課程の学生たちもそんなものがあるのが当たり前、授業なんてお茶の子さいさい。
と思いきや、そうでもないようなのです。
先日、大学生の頃にお世話になっていた教職課程の先生と飲みに行かせていただきました。
毎年、学生さん向けに授業についてや教職についてをお話しさせていただく時間をもらっているのですが、自然と飲んでいる最中もそんな話に。
私の中では、大学生たちにはICTが当たり前になっている教育がスタートラインで、そこからどう試行錯誤するのかという感じなのかと思っていたのですが、実はそうでもないようなのです。
それもそのはず。今、必死に教職課程で模擬授業などを行なっている学生は大学3年生。
彼らが学生真っ只中の高校生の時を思い出してください。
⚡️まともな授業の記憶が実はない!?
そう、彼らが高校生のとき、西暦で言うと2020年、日本どころか世界で新型コロナ感染症によるパンデミックが発生していた時です。
高1を満足に終わらせられず、高2〜3の頃の授業はほとんどオンライン。
中には紙面で課題が配布され、先生の顔もわからずに卒業したという人もいるようです。
文化祭や体育祭といった行事にも縁がなく、生徒と教員とのコミュニケーション、学校現場で培うさまざまな経験、そういったものが体験できていない世代なわけです。
つまり、進路を考え始めたときに一般的な授業をほとんど受けられていなかった学生が、今度は教鞭をとり、授業をしようとしているわけです。
それこそ、オンライン授業の受け方は上手かもしれませんが、そこ止まり。
受けてこなかった授業を自分がやるとなるとうまくいくとは到底考えられません。
私が飲みに行った先生曰く、今年の学生は以前よりも紙とペンを主体とした授業が多く、ICTはおろか、授業スキルも酷いとのことでした。
もちろん全ての学生さんがそうというわけではないと思います。
🧑🏫学生の頃から教職に触れる機会が必要
最近はSNSも普及し、意識が高い学生さんは早くから教職に関わるところに自ら赴いているようです。
私も友人に恵まれたおかげで、よく学生の頃は理科の研修会や教職のセミナーなどに参加して刺激をもらっていました。
その都度、教員としてのやりがいや、「早く先生になりたい」と教職の勉強でネガティブになる思考を持ち上げてもらえたものです。
最近では大学3年生の頃から教員採用試験を受けれるなどの考慮があるようですが、あくまでも教員数の増員を目的とした策略に過ぎません。
3年生で受かったからといって、スキルを上げるために何かをしてくれるかと言われるとそういうわけでもないのです。
だからこそ、必要なのは教育者を育てる教育者。
教職以外の場所でも、教職志望の方へ対してスキルアップを促す機会が必要ですし、技術的なものだけでなく、教員の魅力も伝えられるような環境があるといいなと感じています。
現場の先生方、来年の教育実習は少し大変かもしれません笑。
杞憂に終わるかもしれませんが、未来の教育者の卵をじっくりとしっかりと育ててあげられる教員でいたいものですね。