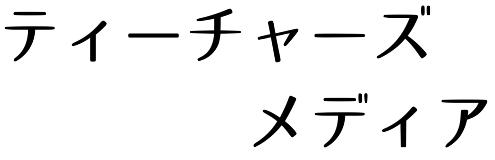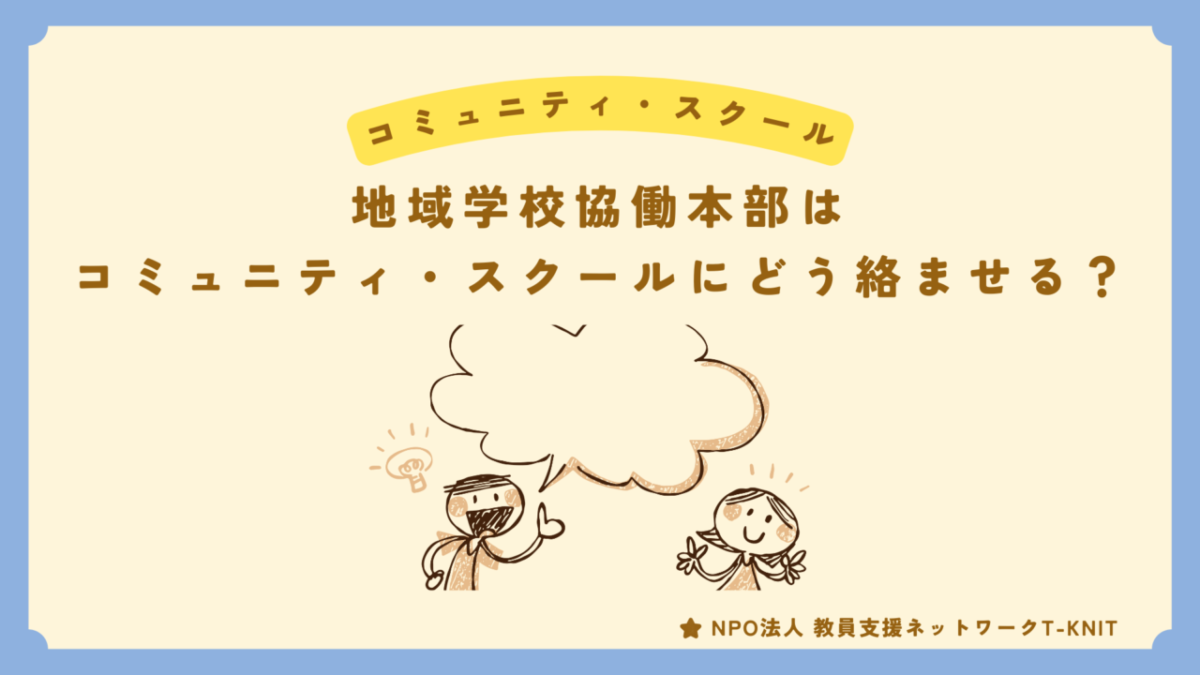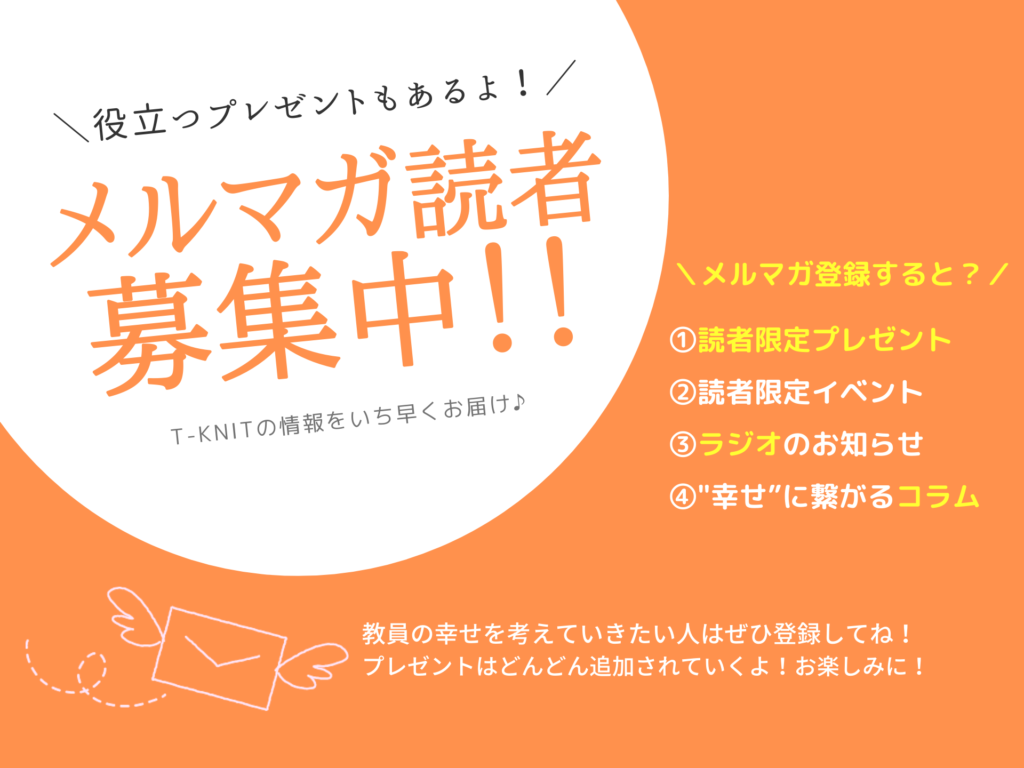- 地域学校協働本部で具体的な活動に迷っている人
- 学校運営協議会と地域学校協働本部をどう一緒に活動していくか分からない人
- 地域学校協働本部はどこを目指して活動すればいいか分からない人
地域学校協働本部…、まだまだ数は少ないですが、確実に設置が増えてきていますね。とは言っても、その中身については課題が多く存在しています。
「地域学校協働本部って具体的に何していくのか分からない」
「学校の小間使いの組織か?また俺ら(地域)に何かさせる気か?」
「学校運営協議会のメンバーばかりで同じような組織じゃないの?」
実際、地域学校協働本部を立ち上げても、実際は学校運営協議会の人ばかりになり、「なぜ分けている必要があるの?」と悩むことも多いのが現状です。
そこで今回は地域学校協働本部は一体どのようにして学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の中に位置づけていくと良いのか?を考えていきます。
地域学校協働本部とは
地域学校協働本部とは、学校と地域が連携・協働しながら、子どもの成長や地域の発展を目指すために設けられた組織です。この本部は、文部科学省が推進している取り組みであり、学校教育と地域活動を結びつける役割を担っています。特に、平成27年12月にその設置が提言され、学校と地域住民が双方向で連携・協働を進める体制が整備されました。
簡単に言うと、地域に点在している組織・団体・企業・個人が、共に協力して子どもたちの成長を支えるネットワークを構築することです。
詳しくは地域学校協働本部とは?に書いているのでお読みください。
地域学校協働本部と学校運営協議会の関係性
では、この地域学校協働本部と学校運営協議会はどう違い、どう連携していくと良いのかをお伝えしましょう。
それぞれ別の目的を持っている組織である
地域学校協働本部と学校運営協議会は、どちらも学校と地域が協力して持続可能な教育環境を築くための組織ですが、それぞれ異なる目的を持っています。
地域とともにある”学校づくり”
学校を核にした”地域づくり”
地域学校協働本部の目的は、地域住民や地域団体が教育活動を通じて、学校を起点とする地域コミュニティの醸成や、地域の人材育成を行うことを目的としています。
一方、学校運営協議会は、地域住民や保護者が学校運営について参画し、意見を反映する仕組みを通して透明性があり、これからの学校の在り方や、地域が欲しい人材を叶える学校教育を実現することを目指しています。

どちらも学校が起点ではありますが、目指していることは少し違うんです。
活動する内容がそれぞれに違う
地域学校協働本部と学校運営協議会は、その活動内容にも違いがあります。
地域と一緒に学校運営について熟議し、運営方針に反映させる
地域や、学校の目指している児童像に向かって学校の支援や、地域課題解決を行う
地域学校協働本部では、理想の児童像に向かって活動を行います。基本的には学校運営協議会とセットで動いているので、学校運営協議会で決まった内容の実現を行っていきます。
例えば、学校支援ボランティアや、見守りボランティア、特別活動の協働といった活動が展開され、地域の方々と子どもたちが触れ合う機会を多く創っていきます。
一方で、学校運営協議会は、学校運営方針の作成や学校目標の設定への関与など、学校の中長期的な運営に関わります。
このように、地域学校協働活動とコミュニティ・スクールの一体的推進が求められる中でも、それぞれの活動範囲は分かれており、異なる次元で子どもたちを中心とした環境作りを支えています。
目的は違えど子どものためは共通事項である
地域学校協働本部と学校運営協議会は、それぞれ独自の目的と活動を持っていますが、その根底にある共通点は『地域の子どもを育む』ことです。
地域学校協働活動を通して、地域住民が直接的に子どもたちと関わり、学びの場や社会経験を提供する役割を担います。また、子どもと直接触れ合うことが少なくなった現代において、世代を超えた交流が生まれやすいと言えます。
一方で、学校運営協議会は、学校環境の向上や教育方針の充実を通じて、子どもたちが安心して学べる場を構築します。学校の働き方改革や、学校ビジョンの再構築など地域が運営に参画することで、より多様な視点から子どもにとって良い環境を生むキッカケになっていくでしょう。
これからの学校と地域の未来を見据えるとき、両者の連携がより深まり、それぞれの強みを生かすことで、地域社会全体で子どもたちの成長を支えることが可能となります。
一体的な推進とは具体的に何をすればいいか
コミュニティ・スクールの中に『一体的な推進』という言葉が出てきますが、一体何をしたら一体的な推進と捉えられるのかについてお話していきます。
方向性と活動を一緒にする
学校運営協議会と地域学校協働本部の両方が同じ最上位目的を共有していることが大切です。
例えば私が支援している学校での最上位目的は『100年先まで続く◯◯(地域名)にする』ことです。
そのために守っていくポリシーもあり、
- 持続可能性のある形で地域コミュニティを作ること
- 何をするかよりもどう繋がりを作るかを大切にすること
- 子どもたちの体験を奪わないこと
を決めています。
このように決めておくことで、活動を行う際の指針になったり、学校運営協議会での熟議の決定打になります。
まさに地域とともに作るグランドデザインの問い直しとも言えるでしょう。

設置当初に決められたらすごいのですが、実際には活動していく中でだんだんと決まっていくことが多いかなと思います。これは学校がすでにグランドデザインを構築し、そこから離れられないからです。
お互いの課題を共有し、解決を図る
一体的推進を行う上でもう一つ大切なことは『地域課題』にフォーカスすることです。
これには2つの理由があります。
1つ目は学校のみの教育方針にしないためです。今までは校長が方針を決めていましたが、地域外からやってきて、1〜3年で異動になってしまうことや、学校教育カリキュラム重視のグランドデザインになっていました。
しかし、実際に大切なのは地域から預かった子どもたちをどう育成し、どう地域に還元するか?という視点が大切です。そのために地域の方々に入ってもらって、地域課題を共有し、先々を見据えた教育を今行う必要があります。
2つ目は地域にメリットを生むためです。先生たちは「学校と地域の連携と言って、地域にボランティアに来てもらえる制度だ」と勘違いしているケースが多々あります。活動する内容だけで言えばそのように見えることもあるでしょう。
しかし、それだけでは地域に何のメリットもありません。「俺たちは学校のためにまた働かされるのか」と言われるのがオチです。そのために地域課題を共有し、子どもたちの育成を通して、地域に還元していく姿勢が先生たちには必要なのです。
課題を隠さずオープンな形で示し合い、解決に向けた具体的な手立てを講じる。文部科学省が提唱する「社会に開かれた教育課程」の実現を目指し、地域住民も積極的に議論や活動に参加することで、持続可能な教育と地域づくりが推進されていくのです。
地域学校協働本部の一体的推進の具体的な事例
では、地域学校協働本部の活動としてどのようなことをやっているのか?具体的な事例を見てみましょう。
地域が学校の特別活動へ参画
地域学校協働本部の一体的推進として、地域が学校の特別活動へ積極的に参画する事例があります。
- 学級活動
- ホームルーム
- 児童会、生徒会
- 遠足
- 合唱コンクール
- 入学式
- 卒業式
- 全校集会
- 朝の会
- 学校祭、文化祭、三世代ふれあいの集い
- 運動会
- 校歌斉唱
- 学年体育着
このような活動はいわば地域づくりの基礎トレーニングです。
例えば、コミュニティ・スクールの枠組みを活用し、地域住民や地元の専門家が町探検に参加することで、子どもたちは普段の授業では学べない知識や技能を習得します。

特別活動を地域の人たちと一緒に企画・実行するだけでも立派な『地域学校協働』となります。
地域の成功・失敗談をキャリア教育として講演
地域住民が自身の経験を子どもたちに伝える講演活動も、地域学校協働活動の一環として行いやすいでしょう。
成功体験や失敗談をもとにした講演は、子どもたちにキャリアへの具体的なイメージを与えると同時に、自分の人生を考える機会を提供します。

地域学校協働本部の支援によって、こうした講演活動が円滑に実施されることで、地域と学校がより強くつながり、地域の人と子どもたちの接点もどんどん大きくなっていくのがメリットです。
地域のイベントに子どもたちが参加
地域の季節ごとのイベントや祭り、清掃活動などに学校の子どもたちが参加する事例も一体的推進の成功例です。
地域住民とともに活動を行うことで、子どもたちは地域の文化や伝統を直接体験し、地域についての理解を深めます。また、地域住民との交流が世代を超えたコミュニケーションの場を生み、子どもたちのコミュニケーション能力の向上や社会性の育成が期待できます。

地域が学校では教えられないことで貢献する好例として使えるでしょう。
学校の活動を地域が支える
授業以外の点で地域が学校に定期的に入るのも良いでしょう。
例えば、見守り活動や、授業支援ボランティアを通じて、地域住民が直接子どもたちに関わる場を作り出せます。さらに、地域住民が学校の安全対策や、行事運営を支えることで、教員の業務負担が軽減され、教育の質の向上につながります。

たくさんのメリットがある取り組みではありますが、多くの地域住民や、保護者はボランティアで来てくれるので敬意を払うようにしていく必要があるでしょう。
地域学校協働本部とコミュニティ・スクールはどう絡ませていくか?
それではまとめです。
地域学校協働本部はコミュニティ・スクールの中では一番アクティブに動いていく場所です。
最上位目的は『子どもたちのため』と同じであるにも関わらず、うまく機能しないことも多々あるでしょう。このような場合に対話の機会を設けず、相手が何に困っているのか?を聞かないと、より溝が深くなってしまいます。
うまく協働するためには『別々なものではなく、同じ目的に向かうけど、やり方が違う』という広い視野が必要なのではないかもしれませんね。
他にも地域学校協働本部に関する記事があります。ぜひご覧ください。
その他、コミュニティ・スクール全体に関するマニュアルもありますので、もっと深く知っていきたいと思っている方はご覧ください。