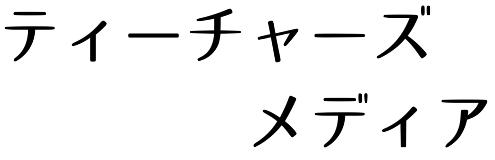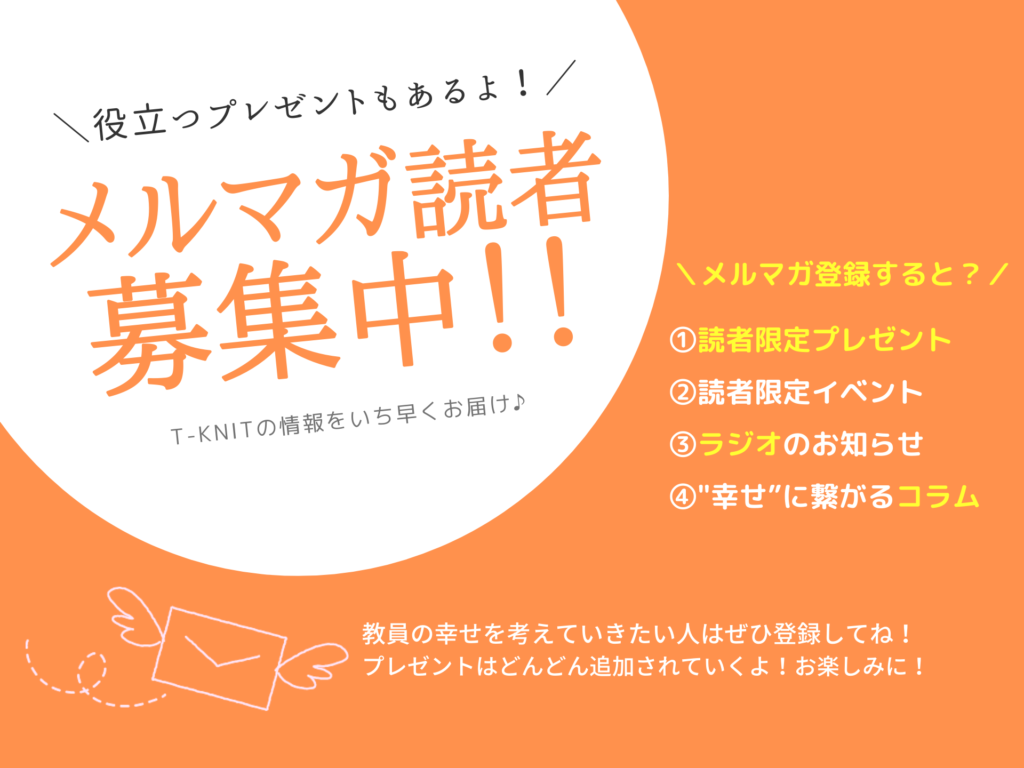「教員がブラックだ!」とニュースで報道されるようになってから、教員の成り手が少なくなったり、多様化により学校教育に持ち込まれるジャンルも増え、ますます教員が働きにくいと感じることも増えています。
そんな世の中なのにも関わらず、教員を支える活動をしている人や、団体は今なお少ないままです。
しかし、そんな中でも私達、T-KNITと同じように『教員支援』を掲げている元教員の方にインタビューを行いました。
一体どのような経緯で、どんなことを行っているのか?
元教員が行う教員支援の世界をぜひご覧ください!
このインタビューは2025年3月31日に実施されたインタビューです。

岩渕 佳宏(ぶっち先生)
Teacher’s Life Design 代表 スクールコーチとして先生が幸せに働ける学校づくり講座を主催。
主幹教諭として5年間病休0の職員室を実現した実績を持ち、学校組織チームづくりの専門家として全国の先生たちの勇気づけを行っている。
\動画で閲覧したい場合はこちら/
岩渕佳宏さんの経歴

今回はよろしくお願いします!早速ですが、自己紹介をよろしくお願いします!

はい。大阪でスクールコーチをしています。
ぶっちこと、岩渕佳宏と言います。
家族が4人いまして、今、42歳の2人の子供の父親です。

なんでスクールコーチになったんですか?

僕、自分自身も昨年の3月までは教員を13年半しておりまして、現場で先生が幸せに働ける学校を作って行くと、子供も輝いたり、先生も生き生きするっていうのが実証ができたり、これは大事だなっていう体験があったんです。
それをまずは近くの学校にとか、知り合いの方の現場とかに広めていったのが始まりですね。
先生が自己犠牲の上で「子供を幸せに」とか、「子供を真ん中に」と言うんじゃなくて、先生も幸せで、「この仕事選んでよかった」と言ってもらいたい。
子供も先生といる中で輝けるというか…学校という場所が好きになったりということが起こっていく社会になれば、絶対日本は良くなるだろうなと思って活動しております。

同じよ!うちの方針と全く同じことを言ってくれている気がする(笑)。

でしたか(笑)。

ちなみにぶっちさんと会うのまだ二回目で経歴がよく分かっていないという状態なんです(笑)。
なので、独立するまでの詳しい経歴を教えてもらって良いですか?

そうですね。教師は小学校で13年半やりました。その中で担任したりとか、学年主任したりとか、教務主任をしていました。
で、教務主任を5年間してた時に、アドラー心理学とコーチングを学んで、それを実践して活かしていくと、病休者が複数出ていた職場で、5年間病休者0で、チーム作りができて、先生が生き生きと働くようになったんですよ。
それプラス、子供たちもそういう先生を見て生き生きとしていくし、親御さんから良いフィードバックももらえるし…。でも、これを自分のいる学校だけが実現できるってなんかやりたいことと違うなーと感じたんです。
もっとフットワーク軽くアプローチできて、サポートをするために独立しました。

すごいですねー。学校の先生の前にはどんな働き方してたんですか?

教育現場に正式に採用されたのが29歳でした。その前は教員免許持ってなかったんですよ。
小学校の先生なんかなれるなんて思ってなくて、大学は楽しんでダンスとかして、就職するよりも、世界を旅していきたいって思って、学力もない、英語も喋れない自分は日本語教師になろうって思ったんですね。
で、いろいろ回れたらイイなって思ってたんですが、やっぱり日本が良いかなーって思う体験があって、大阪に住んで、日本語教師を2校掛け持ちして非常勤で働いていました。

じゃあ、そこから小学校教師に?

いや、これじゃちょっと飯が食えんぞと若い僕は思って(笑)。
でも、教える仕事は好きだったので、家族を養うくらいの収入とかもあって、休みもあったらなぁーって思ってたんです。
そしたら、小学校の教員になる方法を通信で免許取ったよって友達がいたんですよ。
ただ、お金もなかったので、今度はIT企業とかに勤めて給料いただきながら資格をとって2年かけて現場に入ったという感じですね。
教員を支える活動とは

えー、じゃあ、教員を目指してなったって感じだったんですね。それはすごい。
そこから教員を支える活動に入ったと思うんですが…、具体的に何をやってるんですか?

ソルティーとほぼ同じかもしれないですけど、やってるのは『チームビルディング』や、『コーチング』です。
スクールコーチと僕も名乗っているので、肩書き的にはコーチングをベースに、先生方がどんなふうに働けたら幸せなのかとか、どんな現場になって、どんなチームになって働けると自分がよりパフォーマンスが上がるかとかを引き出したり、サポートしています。
個人もやりますが、学校に研修に行かせていただいたりとか、自治体でミドルリーダー研修などをさせてもらっています。

めっちゃやってるやん。
コーチングがベースなんですね。

一番究極は、その個の先生1人1人が幸せに自分らしく働いたら、子供たちにもいい影響があるっていう風にはもうわかってるんです。
なので、先生がいかに幸せに自分らしくこの仕事を選んで良かった、この仲間と一緒に働けてよかったっていう風に働けるかってアプローチしていますね。

学校の外に出たのは一年前ですか?

そうです。本当に1年前の3月31日はまだ職員室で…。去るから迷惑だけかけないように、引き継ぎ資料作りまくって夜9時まで働いて終わったって感じでしたね。
中から外に出てから見る学校の姿

なるほど、1年経って、外に出て感じると、なんか視点が変わると思うんですよ。
その視点が変わって日本の教育を見た時に課題とか、印象とか…何がどう違ったかってことがあったら教えてください。

うーん、課題はありますが、課題よりも先に素晴らしいところのほうが良く見えましたね。
やっぱり日本の公教育ってすごいなって。
うちの娘が夏休み・冬休みの宿題を「丸付けして」って、持ってくるんですよ。娘は今、2年生なんですけど、昔は字もそんなに書けなかった、計算もできなかった。
だけど、冬休みの宿題とか持ってきたら、筆算とか繰り上がりとか、九九とか漢字だって、もう何百字も覚えて書けるんですよ。
で、この変化をほとんどの児童に『当たり前のように』起こしてる事実がすごいなって思っちゃったんですよ。

たしかに。文字と計算がみんなできるって当たり前じゃない国のほうが多いですよね。

そう、離島とか僻地とか関係なく、日本全国で成長を保障してるっていう状態が、まずすごいなって思ったんですよ。
現場にいた時は、当たり前だったし、大変だったし、なんかむしろ2年生の課題が終わってない子に注目しちゃって、「もっとさせなきゃ」とか、「自分うまくいってない」とかっていう、ネガティブなことばっかり言ってたんですけどね。
そこに囚われず生きてて、子供が成長した場面、できるようになったことだけを見た時に、いや、すごいな〜と思って。
うちも娘も楽しそうに学校行ってますが、そうやって楽しい場所も作ってくれてるしね。

なるほどねぇ。先生だったからこその説得力がありますね。

あとは年間研修で何校か行かせてもらった中で、先生方の授業の様子を見させてもらったんですよ。
その時、一斉指導って、なんかちょっと批判されてきてますけど、あの技術って相当すごいなってやっぱ思っちゃったんですよね。
30〜40人、大阪だったらいるんですけど、5時間目の授業の算数で、3年生か4年生だったと思うんですけど、先生がちゃんとテンポ合わせて、「子供が今、どれぐらいキャッチしてるか」って表情と様子から、声掛けの仕方を変えたり、考えさせたりっていうのを調整しながら、授業を一斉指導で進めていくんですよね。
それって実はなかなかできることじゃないんだなと。

たしかに全員が足並み揃えるって簡単じゃないですよね。

確かに個別最適化とか自由進度学習もすごい大事だと思うし、今のニーズに合ってるとは思うんだけれども、昔から一斉指導があったからこそ、型ができて、ある程度の学力や、そもそもの僕らの言語能力とか思考力とかが育っていくベースを作ってくれてる。
学期末ぐらいで、一斉指導ばっかりじゃなくて、係のことを考えてみたりとか、クイズ形式でドリルの問題を出題したりとかって先生が工夫してやってたりすると、子供がものすごい食いついて授業を受けてたりとかするんですよ。
一斉指導は、昭和や明治から形が変わってないなんていう風に言われたり、オワコンなんて言われたりする中でも、すごい工夫しながら、子供のなんか表情とか様子に合わせてやってる。
6時間目でも生き生きしてる教室を見ると、なんかすごい技術だなっていう風に改めて思っちゃったんですよね。
まぁ、6時間ずっと授業はしんどいですけど、その中で遊びを入れたり、対話を入れたり、学級で考える時間も入れたりしながら、1年間1000時間以上やっている公教育がもっとやっぱ見直されるべきだなっていう気持ちの方がちょっと強くなりましたね。

なるほどねー。ポジティブな視点ですね。

そう。今、頑張ってることがすごい批判されたり、学校現場が批判されちゃったりすると、先生が勇気くじかれるだろうなっていうのを見てて感じてます。
でも、こういうポジティブな視点が先生たちの勇気づけになって、その勇気づけられた先生たちが、不登校や、自殺の問題に向き合って、「じゃあもっと子供に合った、子どもが主体になっていくようなものを作っていこう!」っていう流れはいいなと思う。

なるほど、学校や、地域・保護者の誤解というか、齟齬というか…。
もうちょっと理解し合って一緒に取り組んだり、一緒に同じ方向を向いてやっていこうってなると、もっと素敵ですね。

そうですね。
どっちかが淘汰されるというよりは、ベテランの先生の良いところと、若手の柔軟な考え方の良いところ、AIの良いところと、一斉指導・ティーチングの良いところ…。いろんな良いところが重なったらいいんじゃないかなと思ってて。
それぞれの持ち味が重なっていくと、皆さんが満たされるし、自分が貢献できるって、まず、それが先だなって思いますね。
まぁ、僕は先生は幸せになってほしいとか、先生を勇気づけたいっていうのが多分ベースにあるからかもしれないんですけど(笑)。

素晴らしい!その視点、すごく大事ですね。

いや、でも、現場の時は色々思ってましたよ(笑)。
「あれが変われ」とか、「これが困る」、「これだから子供たちが育たないんだ」とか思ってたんですけどね〜。
イチ保護者に近い形になったので、余計に学校のありがたみをね…。子供を1日見てくれる場所という意味でも感謝ですよ。
預けられるから、働きに行けているっていうことも、そういう機能的な部分も学校としてはあると思うんですよね。
子供を子供の中で成長させていくみたいなのもあるしね。
うん、なんか良いとこばっかりを言っちゃって課題を言ってないですけど(笑)。
自身の課題や、これからの展望

そんな活動をしているぶっちさんですけど、ご自身の課題ありますか?

いや、もうそれはありまくりですよ。
自分がやってることがいいものだとは思ってるんですけど、まだ狭い世界に届けるって感じますね。
もっと知ってもらうために、教育分野だけじゃなくて、いろんな方と繋がって活動的にしないといけないと思いますし、もっと自分が持っているコーチングの技術も磨きたい。
まだまだ課題はいっぱいあります。

これ、スクールコーチの活動1本なんですか?

そうですね。そういった課題で言うと、収入も増やさないといけないし…とは思ってます。

いや、でも、それだけで行ってるのがすごいね(笑)。
これは先生個人から依頼が来るんですか?それとも行政経由?

行政から来たら良いんですけど、まだ個別でコーチング依頼とかですね。他にSNSや、口コミかなぁ。
あとは研修受けてもらった方が研修担当の方だったりすると、細い繋がりで自治体の研修に呼んでいただいたりとかはありますね。
自分が長く勤めていた枚方市ってところの研修や、学校研修が多いですね。

今後はこういうことしてみたいとかありますか?

ありますよ。今後は自治体に働きかけていきたいって思ってます。
というのも、単発で小学校に入らせてもらうことがあるんですが、今、大阪府で言うと転任されて1年、2年目の方の精神疾患とかメンタルダウンで病休される方が1番多いんですよ。
そのような方は移動するだけでもストレスになったり、「需要されるかな」っていう需要懸念があります。
そうなると、実力があったり働きたいと思う先生が、休むか、辞めるかを選択せざるを得なくなっちゃったりする。
それを人間関係やチームで防げるなら、防ぎたいなって思いますね。

それはとても大事な活動ですね。

例えば、異動してきたばかりの人が、「ようこそー!」って全力で受け入れてもらうのか、静まり返った雰囲気で「おはようございます…。」ぐらいで受け入れられるかでメンタルって全然違うんですよ。
それってチームの工夫じゃないですか。
会社のアンケートでも対人関係が理由で辞めるが多い。逆に対人関係の居心地が良かったら、「この職場でずっと働きたい」とか、「やりがいを持って働く!」っていうのもデータで出ています。
だとしたら、自分の職員室の居心地が良いとか、会いたい人がいるとか、日曜の夜でも行きたい場所になってるかっていうところが結構ポイントになる。
それは僕たちのチームビルディングとコミュニケーションで作っていけるし、心理的安全性の高い小学校を1個作るんじゃなくて、どこに行ってもこの自治体だったら安心して働けるねっていう、心理的安全性の高い自治体を作りたいっていうのが、今のやりたいことです。

いいね、なるほど!じゃあ、そこは枚方から行きたいということですかね。

いえいえ、声をかけていただけたら、どこでもホンマに行きますよ。
教育委員会の方は、予算や、権限とか、それを作っていくステップとかいろんな苦労は分かっているので、もし、必要としていただけるんだったら、本当に全力で尽力したいなって思っていますね。
先生への投資感覚の克服

あ、一個だけ気になったので質問いいですか?
個人からコーチング依頼を受けてますって言ってたと思うんですが、それってちゃんとお金払ってもらってると思うんですよ。
それってすごいなって感じてて、僕、学校の先生って無料の講座しかあんまり出たがらない印象があるなって思ってるんです。
それってどうしてそうなるんですかね?克服とかできるものですか?

多いですよね。
でも、それは個人の問題っていうよりは仕組みの問題かなと思いますね。
教員って、そもそも研修が年間で組まれてるんですよね。例えば3年目研修とか、10年目研修とかって。
研修っていうもののイメージが『自ら学びに行かなくても組まれてるもの』っていうのが、教員の世界に入ったらあるんですよ。

うんうん、なるほど。

でも、研修の位置付けは主体的に行きたいものなのかというと違うんですよね。受動的だったり、面倒くさいと感じてたり、言ったりする人がいるんですよ。
この背景には、現場がすごい忙しいからっていうのもあったりします。
自分のクラスとか、業務に追われてるので、研修行ってる場合じゃないぐらい大変なのに!って、前向きに受け取ってる方の割合はもしかしたら少ないかなと僕の経験上は感じます。
人権とか、いじめ対応とか、選択系の研修ももちろんあるんですけど全体の総数的には受動的に受けてる方が多いかなぁ。
なんかせっかく自分の実力が上がっていくための学びなんだけど、受動的に受けている文化背景があって活かしきれていないっていうのは、教職員文化の中にある感じはします。

全部無料なんですかー!いや、贅沢だねぇ。

贅沢ですよー。
もう一個言うと研究授業ってあるじゃないですか。
例えば校内で国語の研究しましょうって学校があったら、1〜6年で一本ずつってやるんですが、研究授業をするとめちゃくちゃ成長するんですよ。
なぜって研究するから。

まぁ、本気でやったらそうですね。

これ、子どもが聞いちゃったらどうかなって思うところもあるんですが、その研究自体をやりたがらないとか、受けたくないっていうところはあるんです。
先生は「あなたたち、勉強しなさい!」って言っといて、「先生は勉強しないのかよ」って言われちゃうかもしれないんですが、全員ではないにせよ、実際としてそういう背景がある。
前向きに研究授業したいですっていう人もたくさんいらっしゃる中でも、「面倒だな」って思われたり、「負担だ」って感じるような仕組みや背景があるんですね。
研究授業はすごい負荷が高いです。その負荷で成長はするんですけど、そういった背景から研修自体、外に学びに行くことことに、ちょっとマイナスなバイアスが働いたりするんだなって。
僕は会社員から学校現場に入った一人なので感じましたね。
土日とか夜に学びに行くよりは、「面倒くさい」、「行きたくない」、「お金かけては学びたくない」っていうのを感じるのは0じゃないと。

だけど、そういう主体的に自分が学びたいことを学べるって幸せだよね!自分の人生の目的って何かな?ってマインドセットして受けさせてあげる。
目的に合わせた手段の一つとして捉え直してもらえるようにってやってらっしゃるんですね。

そうですね。
ここはソルティーと同じく壁なんですけどね。
良いものには、やっぱりお金をちゃんと投資して、自分の自己投資にしてもらいたい。
これは僕のコーチングの学びがそうだったので。
コーチング学ぶのは高いお金でした。でも、自分の人生が変わるぐらいの学びだったので、そういうのにはちゃんとお金を投資するっていうことは僕は必要かなと思います。

うん、幸せのために時間とお金を投資しよう!
ぶっちさんの活動を知りたい人へ

はい、ということで、もっといろいろ話を聞きたいところなんですが、時間がだいぶ過ぎてしまったので、終わりに向かっていきたいなと思います。
で、ぶっちさんがやっていることを宣伝したり、お伝えいただけると。

自分としては、今この先生が幸せに働ける学校作りの講座を第3期になりました。昨日、第2期が終わって、皆さん全国から集まってきてくれて、本当にいい学び・良いチームになって終わっていくんですよ。
なんでそういう良いチームができていくかっていうと、どうやったら安心して自分の自己表現できるかとか、どうやったらそういうチームになっていくかっていうステップが体験しながら学べて繋がりができたりとか、コーチングができるようになるからです。
子供に対してもそういう講座をしてます。それは先生が幸せになってほしいからですね。
先生の現場が変わってほしいし、先生自身が幸せになってほしいからっていうのでやってる講座なので、4月は説明会を毎週のようにしていこうと思っています。よかったら来ていただけたら嬉しいです

分かりました!どうやって繋がればいいですか?

色々なSNSやってますけど、Facebookが1番情報発信してるんで、Facebookで『岩渕佳宏』って検索してみてください。

ラジオ聞きました!っていうと特典あるとかないとか!?

説明会とか出てくれたら、実は特典でコーチング体験セッションをちょっとお安くして受けれるようにしています。
説明会は無料なんですけど、出てくれたらそれだけでも勉強になりますし、すぐ使えるエッセンスいっぱい入れますし、その後コーチングを本当に1 on 1で安く受けれますので。

じゃあ先生はとても重要な会ですね。
ということで、今回のゲストはぶっち先生でございました。
ありがとうございました!

ありがとうございました!
まとめ
ついつい学校現場って批判的な目で見てしまいがちですが、中を知れば知るほど頑張っている先生も多いんだなという印象です。
その先生の見えざる努力は学校現場を離れたからこそ、現場の魅力が分かり、伝えられるようになる。これも教員支援の形かもしれませんね。
これからも、頑張って欲しいと思います!今回はありがとうございました!